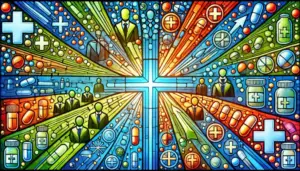薬剤師に「指名制」はありません。
それでも実際には、**「あの薬剤師さんに相談したい」という患者が生まれる一方で、「早く終わってくれれば誰でもいい」**と思われてしまう薬剤師もいます。
では、“選ばれる薬剤師”と“選ばれない薬剤師”の違いは何なのか?
本記事では、両者の行動・考え方・接し方の差を明確にしながら、
「指名されない職業」で“選ばれる存在”になるための視点と実践法を掘り下げていきます。
✅ 「薬剤師は選べない」構造のなかで差がつく理由
患者は基本的に、薬剤師を「指名」することができません。
それでも「この人に相談したい」と感じさせるのは、接点の中で得られる印象・信頼・体験が違うからです。
なぜ差がつくのか?
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 接客時間が短い | わずか数分で印象が決まる |
| 顔・名札の印象 | 名前を覚えられた薬剤師は信頼されやすい |
| 不安に気づく姿勢 | 情報ではなく「気づき」が信頼の種になる |
| 自信と共感のバランス | 押しつけでも不安感でもない“ちょうどよさ” |
つまり、同じ内容を伝えていても「伝わり方」と「印象の残り方」が違うのです。
📉 選ばれない薬剤師にありがちなNG行動
① マニュアル的な説明を早口で一方的に話す
→ 「録音された音声を聞いているようだった」と思われてしまう
② アイコンタクトや表情がない
→ 視線を合わさず説明されると、“本当にこちらを見ているのか”と不信感を持たれる
③ 患者の話をさえぎってしまう
→ 「質問しにくい空気」を生む原因に。最も印象が悪くなる要素のひとつ
④ 不安をスルーする
→ 「この薬、副作用が怖いんです」と言われた時に「大丈夫ですよ」とだけ返すと、不安が置き去りにされる
🧠 患者が“選ぶ”薬剤師の共通点とは?
選ばれる薬剤師に共通しているのは、スキルより“姿勢”の違いです。
① 「答える人」ではなく「聴く人」
- 質問に即答するのではなく、「まず背景を聞く」姿勢がある
- 「なぜそう思ったのか」まで掘り下げようとする
② 説明ではなく“納得”をつくる
- 「この薬はこう飲んでください」ではなく、
→「このタイミングで飲むと、生活の中でも忘れにくくなりますよ」
→ “患者の行動設計”を一緒に考える
③ 名前を名乗り、相手の名前も覚える
- 「○○さんですね。私は〇〇薬剤師です」
→ このやりとりがあるだけで信頼構築の第一歩になる
④ 不安や違和感に丁寧に向き合う
- 「副作用が出そうで不安」という言葉に
→「どういう副作用を一番心配されていますか?」と掘り下げる
→ 不安の中身を“整理”することで安心感が生まれる
💬 実際に「選ばれる薬剤師」の体現行動例
| シーン | 選ばれる薬剤師の対応 |
|---|---|
| 初回服薬説明 | 「他に不安な点はありますか?」と、終了後に質問機会をつくる |
| 再来局時 | 「前回の薬、お変わりありませんでしたか?」と記憶をベースに接する |
| 飲み方の工夫相談 | 「この薬、食後が難しいときはいつ飲んでいらっしゃいますか?」と患者の生活に合わせる |
| 高齢者対応 | ゆっくり・大きめの声・図解の活用など非言語サポートも併用する |
📈 “顔が見える薬剤師”はリピート率と満足度が高い
調査では、薬剤師の名前を覚えている患者ほど、薬局に対しての信頼度・再来率が高いことが明らかになっています。
- 名前を覚えてもらっている薬剤師の対応に「とても満足」と答えた人は全体の70%以上
- 「前回と同じ薬剤師に相談したい」と希望する声は高齢者層で特に多い
🏥 “指名されない職種”で選ばれるための戦略
1. 自分を「見える存在」にする
- 名札、挨拶、軽い自己紹介などで存在感を可視化
2. “次回につなぐ関係”を意識する
- 「次の検査の結果を教えてくださいね」など、継続性のある会話設計
3. 相手の“価値観”にアプローチする
- 「この薬が苦手」→「味?形?過去の経験?」と掘り下げて共感を示す
✅ 結論:「薬の説明」ではなく「人の支援」ができる薬剤師が選ばれる
選ばれる薬剤師に必要なのは、
- スキルの高さよりも相手に合わせる柔軟さ
- 知識の多さよりも伝え方と寄り添い方
患者は、“薬”ではなく“自分”を見てくれる人を信頼します。
薬剤師が“見られる側”から“見ようとする側”へ転じたとき、
その瞬間から、「誰でもいい」ではなく「あなたに聞きたい」と思われる存在へと変わるのです。