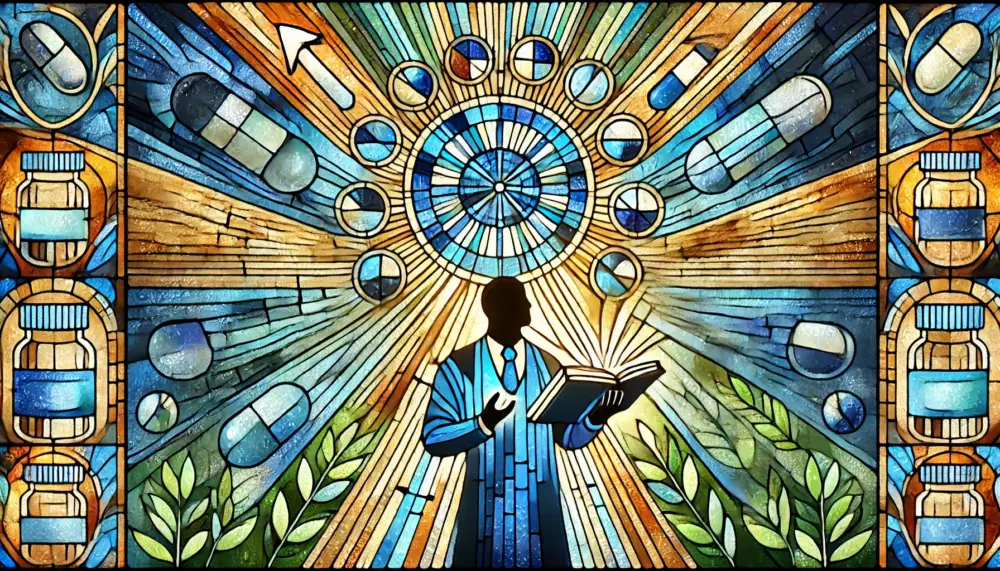薬剤師として、生涯にわたって「何を目指すか」を自ら設計することは、これからの医療・社会が変化を続ける中でますます重要になります。本リストは、「キャリア設計」「スキルアップ」「自己理解/自己成長」の観点から、薬剤師が読むべき4冊を選び、その特徴と比較を通して、自分にとってどの本がいつ・どのように役立つかを考える手がかりを提供することを目的としています。若手・中堅・学生・管理職、どの立場の薬剤師であっても、自身のキャリアに対してより主体的に歩むためのヒントを得られるような構成を心がけました。
薬剤師の新しいキャリアデザイン戦略〜自分らしい人生を歩むために!“33歳までに読む本”
著者:流石 学/長谷川 周重
発売年月:2022年6月28日
概要(専門的視点での要点整理)
この本は、薬剤師としてのキャリアを「自分から見たもの」だけでなく、「外部環境・市場から評価される価値(マーケットバリュー)」という観点で設計することを主眼としています。著者およびキャリア支援の立場から、「これからの薬剤師が何をできるか」「どこまで求められているか」という問いを投げかけ、現実とのギャップを可視化してキャリア戦略を立てるための道具を提供しています。
構成としては、“学生時代/就職直後/30歳前後/40歳前後”などキャリアのステージごとの転機や判断のポイントを、薬局・病院・女性薬剤師・キャリア実現型という4つのケーススタディから論じ、それぞれに対して「何が市場で価値を持つか」「何を準備しておけば後悔しにくいか」が整理されています。実践的なキャリア志向の薬剤師、あるいは将来のポジショニングを考えたい中堅薬剤師にとって、理論と事例の両輪で使える内容です。
評判・口コミの主な傾向
肯定的意見
- 多くの読者は、「薬剤師でありながらキャリア支援/コンサルティングの視点を持つ著者たちだからこそ、市場のトレンドや評価軸をきちんと届けてくれる」と感じており、漠然とした将来不安の整理に有効、という声があります。
- 実践的で“すぐに使える視点”が多い、という評価。たとえば、「現在の職場でできることをまず考える」「自分のマーケットバリューを客観視する」というフレームワークが明確なので、行動の方向性を定めやすいとの意見。
中間的・特徴を指摘する意見
- ケーススタディ形式やエージェントとの対話形式を好む人には読みやすいが、それが冗長だと感じる人もいる。特に経験豊富な薬剤師にとっては“当たり前”と感じる部分も含まれており、新しい情報・気付きが限られていた、という見方も。
- 「33歳までに読む本」というタイトルが目立ち、若手向けという印象を持たれがちだが、実際は中堅層にも役立つ内容があるため、中間層がタイトルに引いてしまわないか、という指摘も。一部の読者からは「自分にはちょっと早いテーマだ」と感じられることがある。
批判的意見・留意点
- 読者によっては、理論的・戦略的部分が強いため、「現場での細かいスキル」「薬剤調剤や服薬指導等の具体的な臨床/コミュニケーションスキル」のヒントが少ない、と感じることがある。キャリア設計には有益だが、日々の業務改善には即効性が薄い部分も。
- 電子書籍版の可読性・注釈・検索機能など操作性の制約が指摘されており、学びのためのまとめや備忘・引用用途で使いたい人には、紙版をおすすめする声がある。
なぜこの本がお薦めか(プロがテーマを理解する上でのポイント)
- マーケット志向のキャリア観を持たせてくれる
薬剤師の仕事・キャリアを“職場内評価”だけでなく、“業界全体/求人側の見方”から自分をどう評価すべきかを知ることは、将来の意思決定(異動・転職・業務の拡張・対応力の強化など)において非常に重要です。この本はその“外の目”を養う訓練になる。 - 自己設計の戦略ツールとしての実用性
キャリア設計という大きなテーマを、自分の人生ステージごとの具体的ケースを通じて整理できるため、「なんとなく不安」という漠然とした領域をクリアにしていくことができる。特に30代になると見落とされがちな“自分が何を市場で価値とされているか”“どこを伸ばすべきか”“交渉可能な条件は何か”を意識させてくれる。 - 職場を変えることが目的ではない視点
転職を前提とするのではなく、今の環境の中でどうキャリアを積むか、あるいは変える必要があるとしたらどのような準備をすべきかという選択肢の設計が強調されている点。これによりキャリアの“持続性”や“安定性”を考える薬剤師にとっても意味が深い。
これが私の薬剤師ライフ 6年制卒50人がキャリアを語る
著者/編集:日経ドラッグインフォメーション(編集)
発売年月:2022年4月28日
概要(専門的視点での要点整理)
この本は、「6年制薬学部卒」の薬剤師50人が、自身のキャリアを語るエッセイ集+インタビュー集の形式で構成されています。出版は、薬学教育が6年制になってからしばらく経ち、1期生卒業後10年が経過した時点での“先行経験者たちの歩み”を通じて、薬学生や若手薬剤師だけでなく、中堅世代もキャリア観を見直す機会を提供することを意図しています。
対象者は主に20〜30代。薬局、ドラッグストア、病院、大学、製薬企業、治験コーディネーター、公務員など多様な職場に進んだ人が含まれており、進路の幅広さとその選択にいたった理由・失敗・悩みなどのリアルな声が収められています。キャリアの入口、転職や役割変更、専門性の発揮、ワークライフバランス等、テーマが多岐にわたるため、読者は“自分はこういう道を歩みたい/歩む可能性がある”というモデルを複数見つけられます。
ページ数は336ページ。立場に応じたキャリア判断・自己評価・将来予測など、実務的かつ心理的に響く話が多く含まれています。
主な口コミ・評判(特徴と意見の整理)
肯定的意見
- 多様なキャリアパスが紹介されているため、「薬学生や若手薬剤師が将来の選択肢をイメージしやすい」と評価されている。どのような進路が現実に“有人”かを示すことで、自分の可能性を広げる視点を提供するという見方。
- 執筆者たちの“悩み”や“失敗”談も抑えてあり、成功談だけでなく挫折や迷いも含まれていることで、リアリティと共感度が高いとされる。「先輩もこういう壁を乗り越えてきたのか」と思える点が励みになるという声。
- 若手薬剤師だけでなく、中堅薬剤師にとっても「自分のキャリアが周囲とどう違ってきているか」「進むべき方向性の修正点」を考える機会になるという意見。
中間的・特徴を指摘する意見
- “就職/転職動機”や“仕事内容の選択理由”に比べて、「具体的なスキルの磨き方」「現場で遭遇する問題への対処法」「日常業務で使えるノウハウ」は少なめ、という見方がある。職業観・人生設計的な側面が前面。
- タイトルが「6年制卒」に限定しているため、自分が4年制卒・留学経験あり・他業種経験あり…等のバックグラウンドを持つ薬剤師にとっては、自分との違いを感じて“当てはまらない”と感じる部分がある、という意見。
- キャリア成功の事例が多いが、特筆すべき“失敗”や“長く悩んだ末の選択”の記述が浅いと感じる読者もいて、“滑らかなキャリアの羅列”との印象を持つことも。
批判的意見・留意点
- 学生向けとして期待する「就活ノウハウ」「企業を選ぶポイント」「面接準備」などの具体的指針はあまり含まれておらず、その点を期待して購入した学生からは「ちょっと物足りない」という意見がある。
- 執筆者の分布に地域・大学による偏りが見られる(出身大学や大学地域に関する偏り)という指摘があり、「全国の薬学部卒業生の中で代表的な50人とは言い切れないのではないか」という批判がある。
- 女性薬剤師の執筆者数が少なめという声も。子育て・育休・ワークライフバランスといった“女性のキャリア断面”については触れられてはいるものの、両立や復帰の具体的な戦略についてもっと深く知りたい人には物足りない部分がある。
評価を深掘り → テーマ理解にとってなぜお薦めか
この本がお薦めな理由を、キャリア設計や薬剤師としての専門性・将来戦略の観点からさらに掘ると以下の点が挙げられます:
- 実証的なキャリアモデルの提示
50人というサンプル数があることで、「こういう道を歩んだ人が実際にいる」という具体性が担保されており、理論だけでなく“現実モデル”として活用できる。例えば、薬局だけでなく、ドラッグストア、病院、企業といった業界間の移動や、キャリアチェンジをしたケースなど、多面性がある。 - 心理的・職業的“壁”を見せてくれることの価値
キャリアが順調な人ばかりでなく、悩み・転機・迷いを抱えた経験を語る人がいることで、「成功」の裏にある苦労や努力が見える。これによって読者は自分のキャリアの途中で何が起こりうるかを予測しやすくなり、備えや心構えを持ちやすくなる。 - 進路選択の“比較軸”を得る
執筆者50人の多様な進路を比較することで、「自分がどの軸(臨床重視、研究・大学/病院か、企業か、転勤や移動を許容できるか、専門認定を取るか等)」をどこに置くかという選択肢が可視化される。この比較軸を持つこと自体がキャリアデザインでは非常に重要。 - 未来を見据えたキャリア作成の観点
薬剤師業界・薬学教育制度の変化や、6年制卒の薬剤師1期生が“中堅”になってきたという状況、社会・医療・制度の変化に応じてキャリアの要請が変わってきているという文脈が随所に示されている。これにより、読者が“今後10年・20年で何が必要になるか”を考えるヒントが得られる。
病院薬剤師のための スキルアップ×キャリアアップガイド ~学びと評価の指標
監修:全国国立病院薬剤部科長協議会
発売年月:2021年2月25日
概要(専門的視点での要点整理)
この本は、病院薬剤師がキャリアの各ステージ(新人〜薬剤部長等)で求められる “知識・技能・態度” を体系的に整理し、それぞれのステージでの到達目標を明示しているのが特徴です。具体的には、一般目標(GIO: General Intended Outcomes)と行動目標(SBO: Specific Behavioral Objectives)という2種類の目標設定を用いて、病院薬剤師の成長プロセスを可視化しています。
内容の焦点は、「学びの段階ごとの基準を明らかにすること」と、「評価指標として何を用いればよいか/使えるか」を示すことにあります。例えば、業務遂行能力・専門性の獲得・院内外の調整/連携・指導力・後輩育成など、多岐にわたる領域で各段階で期待される行動が整理されており、単なる理念書ではなく、実践現場で目に見える形で活用できる仕様です。
また、監修団体が病院薬剤部科長という現場のトップレベルであることから、評価・育成・制度設計・研修プログラムなど実務上の制度結びつきが想定された内容が多く、病院組織内での人事・能力開発に関心がある薬剤師にとっては “自組織との比較・改善” の材料になる記述が豊富です。
主な口コミ・評判(特徴と意見の整理)
肯定的意見
- 多くの読者は、「キャリアステージごとの目標」が明確に示されている点を高く評価。「今自分がどこにいるか」「次ステップに何が求められているか」が理解できるので、成長設計を具体的に描けるとの意見があります。
- 実際に病院で薬剤師育成に関わる立場の人(研修担当者、師長・科長など)から、「評価制度や育成プランを見直す際の指針になる」「新人教育プログラムの設計に取り入れた」「自部署と他院とのギャップを測る尺度になる」という声も。
中間的・特徴を指摘する意見
- 目標設定が組織的・制度的・管理的な観点から書かれているため、個人のモチベーションやキャリア希望(研究・独立など)と少し方向がずれることがある、との見方。つまり、「組織内での評価に重きを置く内容」であって、必ずしも“自分のやりたいこと”を中心に据えているわけではないという指摘。
- また、行動目標(SBO)が具体的な内容を示している分、業務が小さく定められていない/曖昧な部分もあり、自部署での“解釈”や“落とし込み”が必要、という声がある。
批判的意見・留意点
- 日常業務に追われている薬剤師からは、「目標達成の指標は示されているが、そのための具体的な学習リソース・導き方・時間配分のヒントが不十分」という意見。スキルアップやキャリアアップを目指すには、まず“どのように学ぶか”が重要だが、その戦略部分に対する指示が弱いと感じる人も。
- また、病院規模・地域によって求められる役割がかなり異なるので、本書の目標が必ずしもすべての病院でそのまま適用できるわけではない、という留保がある。小規模病院や地域病院では、リソースやスタッフ構成から“すべての行動目標”が現実的でないケースがある、という声。
専門的な深掘り → テーマ理解にとってなぜお薦めか
この本を読むことで、薬剤師・薬剤部のキャリア設計および病院組織の育成・評価制度について深く理解し、実践できるようになるポイントを以下に挙げます:
- キャリア段階ごとの“期待値の可視化”
新卒・中堅・上級・管理職といった各ステージで“何ができれば良いか”をGIO・SBOという形式で具体的に書き出しているため、自身の立ち位置を把握しやすい。これは自分の強み/弱みを把握し、学習・研修計画を立てる際のベースラインになる。 - 組織運営・人材育成との整合性
病院薬剤部科長協議会という実務責任者層が監修しており、他院との比較・標準化の観点、研修の制度設計・評価制度の見直しといった組織マネジメントに使える内容が多い。個人だけでなく、組織の視点・制度設計の視点を持ちたい薬剤師・管理職には非常に役立つ。 - 実用的行動指標の提示
単に「もっと専門性を高めよう」「調整力を持とう」という抽象的な言葉だけでなく、「~を実行する」「~を報告できる」「~を調整できる」といった行動に落とし込まれた指標があるため、自分や所属部署で具体的な評価制度を作る際の素材になる。 - 自己評価 → 組織内評価 →キャリア交渉への利用可能性
この種の目標・評価指標が整理されていると、自己評価を整理するだけでなく、上司との面談や評価時・異動交渉時に「自分の現在のステージ」「次のステージに求められること」「不足部分を補うための具体策」を示す根拠として使える。そういう意味で、“働くプロ薬剤師”がキャリアをアクティブにマネジメントするためのツールとして有用。
大学のキャリア教育にも使える 薬学生・薬剤師のためのキャリアデザインブック Ver.3
著者:西鶴 智香
発売年月:2025年3月(ver.3)
概要(専門的視点での要点整理)
本書は、「薬学生・薬剤師」が自分のキャリアを能動的に設計する力を育てる目的で作られており、大学の“キャリア教育”の科目やワークショップで使えるようワークシート形式の構成を持っています。キャリア形成理論・自己理解・医療制度の背景・“働く”とは何か/プロフェッションとは何か、などの基礎から入り、自己肯定感・自己効力感・言語化力・コミュニケーションスキル・リーダーシップなど“人間力/社会人基礎力”の育成を重視しているのが特長です。
内容構成は次の通りで、学びやすさと実践性のバランスが取れています:
- キャリア教育そのものが育てるべき力
- キャリア・キャリアデザインの理論
- 薬学生・薬剤師に特有のキャリアデザイン力
- 日本の医療制度・将来予測と課題認識
- 自己理解(自己肯定感・自己効力感)
- エンプロイアビリティ(社会人基礎力、言語化/コミュニケーション力など)
- プロフェッションとプロフェッショナリズム
- 多様なキャリアパスと薬学部卒業者の実際
- 最終的に「自分がつくるキャリアデザイン」を描く
また、各章に“書き込み式のワークシート”が付属しており、自分自身の価値観・強み・弱み・医療・薬剤師として何が求められているか等を整理できるようになっており、受動的に読むだけでなく、参加・思考が促される構造になっています。
ページ数は135ページで、B5判。比較的読み込みやすく、学生用教材や研修用資料としても取り扱いやすい分量です。
主な口コミ・評判(特徴と意見の整理)
肯定的意見
- “書き込みワークを通じて自身を整理できる”という点が評価されており、漠然とした将来像を持てない学生や早期からキャリアを考えたい薬剤師見習いにとって実践的、という声があります。
- また、プロフェッションや医療制度の章など、「薬剤師という職業を社会制度・制度変化の中でどう位置づけられているか」を学べる点が好評。「薬剤師としての自分とは何か」を考える上で理論的な裏付けが得られるとの意見があります。
中間的・特徴を指摘する意見
- 内容が“基礎的・概論的”な部分が多いため、すでに社会人・薬剤師として一定のキャリアを積んでいる人には“物足りない”章もあるという見方があります。理論がしっかりしている分、応用や具体的行動案が浅いと感じる部分もあるようです。
- また「自分を知る」系の章は共感しやすく役に立つが、自己肯定感の育て方やコミュニケーション・言語化力向上の具体的トレーニングが少ないという指摘も。理論とワークシートはあるが、継続して使っていくトレーニングプランなどは読者側で工夫が必要、という意見です。
批判的意見・留意点
- 学生用・教育用としては非常に良いが、実務薬剤師がキャリアのある程度進んだ段階で読むには“次をどうするか”“専門性をどのように深めるか”“異業種との連携/マネジメントをどうするか”といった実践的内容が不足しているとの批判があります。
- 医療制度や将来予測の章は、データの更新頻度や地域差・病院・薬局環境差を反映していないと感じる読者も。自分の置かれている環境と、この本の一般論が一致しない部分があるため、“改変・補足して使う”必要があるとの意見。
専門的な深掘り → テーマ理解にとってなぜお薦めか
この本が“薬学生および薬剤師キャリア設計”を理解する上で価値が高い理由を、以下の観点から深掘りします:
- 早期キャリア自覚の促進
薬学生のうちから「働くとは何か」「どんな価値観でキャリアを選ぶか」を問うことで、大学での授業・実習・インターンシップなど、将来の選択肢を自分から判断できるようになる。キャリア迷走を未然に防ぐ効果が期待できます。 - 自己理解と社会的適性との橋渡し
自己肯定感・自己効力感・言語化力といった“自分の内面”を深める章と、医療制度・エンプロイアビリティといった“社会・制度・他者から見られる自分”を結びつける章が対になっており、自分の価値観・強みを社会でどう活かすかを考えるためのフレームが与えられます。 - 大学・教育現場で使える構成
教員やキャリア教育担当、薬学部の科目やワークショップでそのまま教材として使える構成。ワークシート形式で参加型。授業で扱うテーマ(キャリア理論・プロフェッション性・自己理解等)を章立てで網羅しており、指導者にも使いやすい。 - 薬剤師・薬学生双方への汎用性
学生段階でこれから社会人になる準備をする人にとっても、有資格薬剤師として自分のキャリアを再考する人にとっても、理論・制度・自己認識・思考整理という共通の基盤が提供されており、どのキャリア段階でも“自分でデザインする”姿勢を養う点で有用。
書籍比較と総まとめ
| 書籍 | 対象読者 | 強み | 弱み/限界 |
|---|---|---|---|
| 薬剤師の新しいキャリアデザイン戦略〜自分らしい人生を歩むために!“33歳までに読む本〟 | 20〜30代(特に30歳前後)の薬剤師。キャリアをどう設計すべきか漠然と悩んでいる人。今の職場・業務に疑問を持っている人。 | ・マーケットバリュー(市場から見た評価)という視点を明示していて、「薬剤師として何が求められているか」が外側からの目で見える。 ・ケーススタディ(病院・薬局・女性薬剤師など)で多様な状況を想定し、自分に近いモデルを見つけやすい。 ・“職場を変えることだけがキャリアアップではない”という考えを重視しており、今の職場でどう動くか/どこを伸ばすかを考えるアプローチが実践的。 | ・“33歳までに読む”という副題が若手中心、またタイトルが示す年齢枠が“自分にはもう遅いかも”という印象を与えてしまう人もいる。 ・実務スキル・専門技術の深掘り(調剤・臨床知見など)の具体的トレーニングが多いわけではない。行動指針・考え方の整理が主体。 ・現場・職種・薬剤師の置かれた環境によっては、市場情報の適用可能性が異なる(都市 vs 地方、病院 vs 薬局等)。 |
| これが私の薬剤師ライフ 6年制卒50人がキャリアを語る | 薬学部を卒業した若手~中堅薬剤師。特に6年制卒の薬剤師。学生で進路を考えている人も。 | ・実際に進んだ人の“リアルな声”(成功だけでなく悩み・葛藤・失敗も含む)が豊富。進路の選択肢の幅が見える。 ・「自分とは違う道」「自分に近い道」を比較できる点が、将来を描く際の刺激になる。 ・読みやすく親しみやすい語り口。キャリアのストーリーが具体的で“他人事”と思えない。 | ・ストーリー中心なので、キャリア理論・制度的枠組み・評価指標といった抽象的・構造的な内容は薄め。自分のキャリア設計ツールとして使うには補足が必要。 ・一つの進路・境遇に依存した経験の部分が多く、それをそのまま自分に当てはめるのは危険。 ・いくつかの分野・地域の薬剤師が多く含まれていない/偏りがあるという指摘あり。 |
| 病院薬剤師のための スキルアップ×キャリアアップガイド 学びと評価の指標 | 病院薬剤師(新人〜管理職)、研修担当者・薬剤部科長など、病院組織内で能力開発を考えている人。 | ・キャリアステージごとに「何をできればよいか(知識・技能・態度)」が非常に明瞭に示されていて、自分の現状と到達目標との差を具体的に把握できる。 ・評価指標として実務に落とし込める内容が多く、新人教育や研修制度設計に使いやすい。 ・幅広い領域(業務/調剤/医薬品制度/臨床研究/医療安全/マネジメント等)を網羅しており、「どの領域を伸ばす必要があるか」を見極めるのに便利。 | ・対象が“病院薬剤師”であるため、薬局・ドラッグストアなど他の職場には直接的な適用性が低い部分あり。 ・非常に体系的・制度的・組織的なので、“柔軟性”が少ない。個人が“自分らしさを重視するキャリア”を設計する上では、補足的な思考が必要。 ・実践現場と制度・ステージ目標とのギャップを埋めるための具体的なリソースや手法(研修先・メンター探しなど)の部分が乏しい、という声あり。 |
| 大学のキャリア教育にも使える 薬学生・薬剤師のためのキャリアデザインブック Ver.3 | 薬学生、薬学部のキャリア教育関係者、新人薬剤師/キャリアをこれから設計しようとする人。 | ・自己理解・言語化力・プロフェッション性など基盤力の育成に重きを置いていて、キャリアの根っこを育てるのに適している。 ・ワークシート形式で、実際に自分の思考を整理できる設計。思考を“書く/対話する”形で可視化できる。 ・医療制度・将来予測の章を含んでおり、「外の環境」を知ることでキャリア設計の幅を理解できる。 | ・基礎的・概論的な内容が中心で、すでにキャリアを積んでいる人には新しい知見が少ない可能性。 ・専門性を深めたい・マネジメントや専門技能を磨くための具体的手法や応用例は限定的。 ・制度や環境の変化(地域差・病院・薬局による差)をすべてカバーしているわけではないので、自分の環境に応じた読み替えが必要。 |
総合比較とまとめ
- キャリア理論 vs ストーリー vs 評価基準 vs 自己理解
4冊の中では、それぞれ立ち位置・目的が異なります。理論と市場視点を重視してキャリア戦略の枠組みを与えるもの(「薬剤師の新しいキャリアデザイン戦略」)と、実際の経験者の声でキャリアの可能性を感じさせるもの(「これが私の薬剤師ライフ」)と、制度的に何が期待されているかをステージ別に示すもの(「病院薬剤師のためのスキルアップ…」)と、自己理解・キャリア教育に使える入門的/基盤的なもの(「キャリアデザインブックVer.3」)。 - 対象層による使い分けが重要
若手・学生なら自己理解を促す本やストーリー集から入り、キャリア設計の感覚を掴むのがよい。中堅以上/病院勤務者なら制度的指標や評価基準を提示してくれる本を併用することで、自分の現状を客観的に見て改善点を明らかにできる。 - “自分らしいキャリア”を描くためには複数冊を組み合わせるのが効果的
例えば、「キャリアデザイン戦略」で市場・外部評価軸を学び、「ストーリー集」で実例から可能性と悩みを知り、「スキルアップガイド」で具体的ステージ目標を得て、「キャリアデザインブック」で自己理解や言語化力を磨く…という流れが、キャリア設計を“思いつき”で終わらせず、実践に結びつけるために有意義。 - 共通するポイント
全ての本に共通しているのは、「薬剤師として何ができるか/何が求められているか」という“外との接点”を意識させること。医療制度・評価制度・勤務形態・働き方の現場変化などを無視せず、自分のキャリアを社会・制度・マーケットの中で設計していく視点がいずれの本にもある。