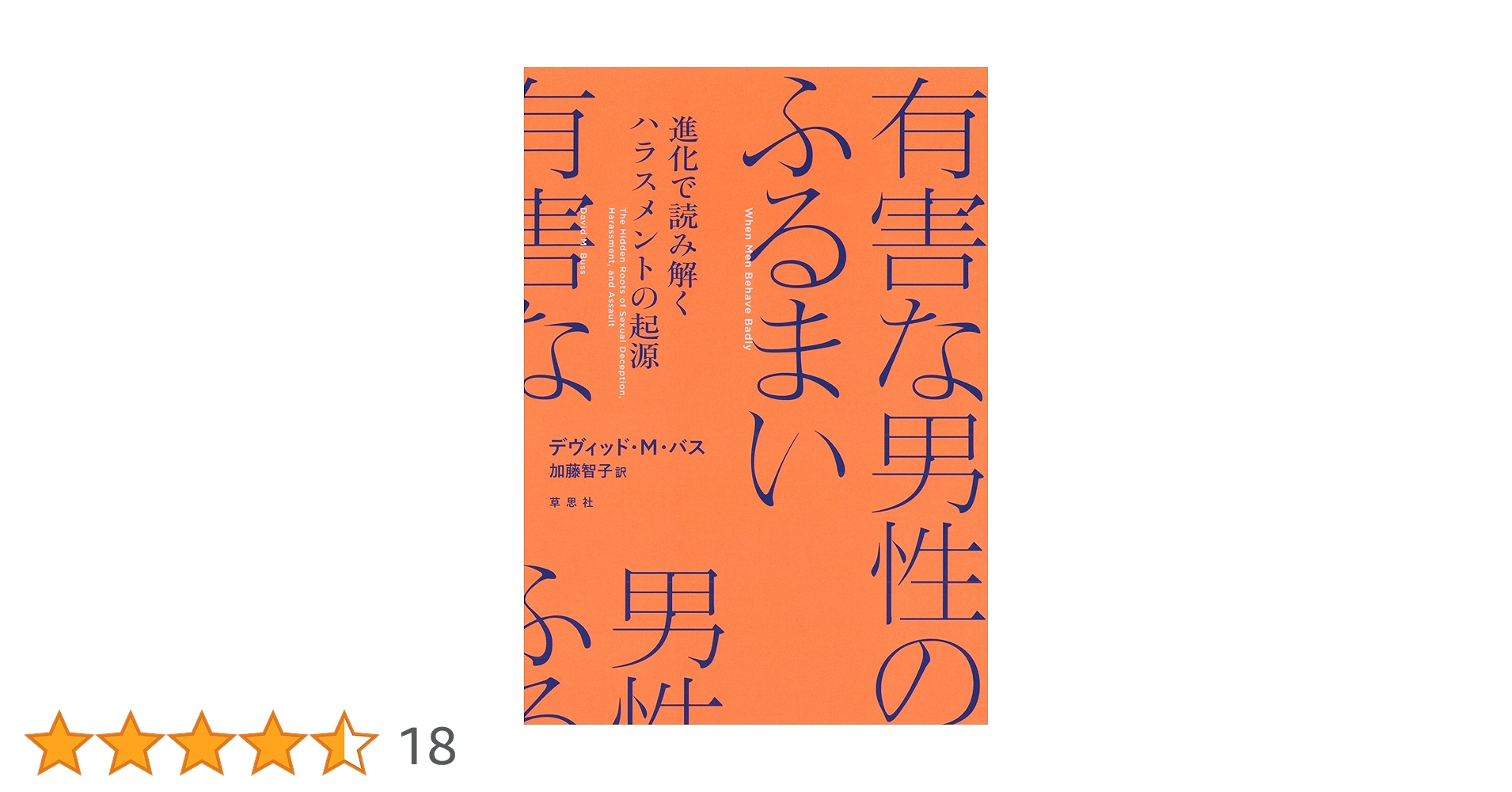Netflixドラマが突きつける「有害な男性性」というテーマ
Netflixのドラマ『アドレセンス』は、青春群像劇の体裁をとりながら、実際にはとても重たいテーマを扱っています。それは「有害な男性性」や「マノスフィア(男性至上主義的なネット文化圏)」と呼ばれるものです。主人公たちが抱える葛藤や、仲間との軋轢、恋愛の中で表出する攻撃性や支配欲は、単なる思春期の“揺らぎ”にとどまりません。そこには、現代社会におけるジェンダー観や、インターネット上で拡散される価値観が色濃く反映されています。
例えば、ドラマの中で描かれる「男は強くあるべき」「支配しなければならない」といった考え方は、現実世界でも多くの若者がSNSや掲示板を通じて触れているものです。それは時に“マノスフィア”と呼ばれるオンライン・コミュニティで強化され、女性嫌悪や暴力的な男性性の正当化につながることがあります。
『アドレセンス』を見て胸がざわつくのは、このようなテーマが決してフィクションだけの話ではなく、現実と直結しているからです。そして、この問題を理解する手がかりとして紹介したいのが、進化心理学者デヴィッド・M・バスの著書『有害な男性のふるまい: 進化で読み解くハラスメントの起源』です。
『有害な男性のふるまい』の概要
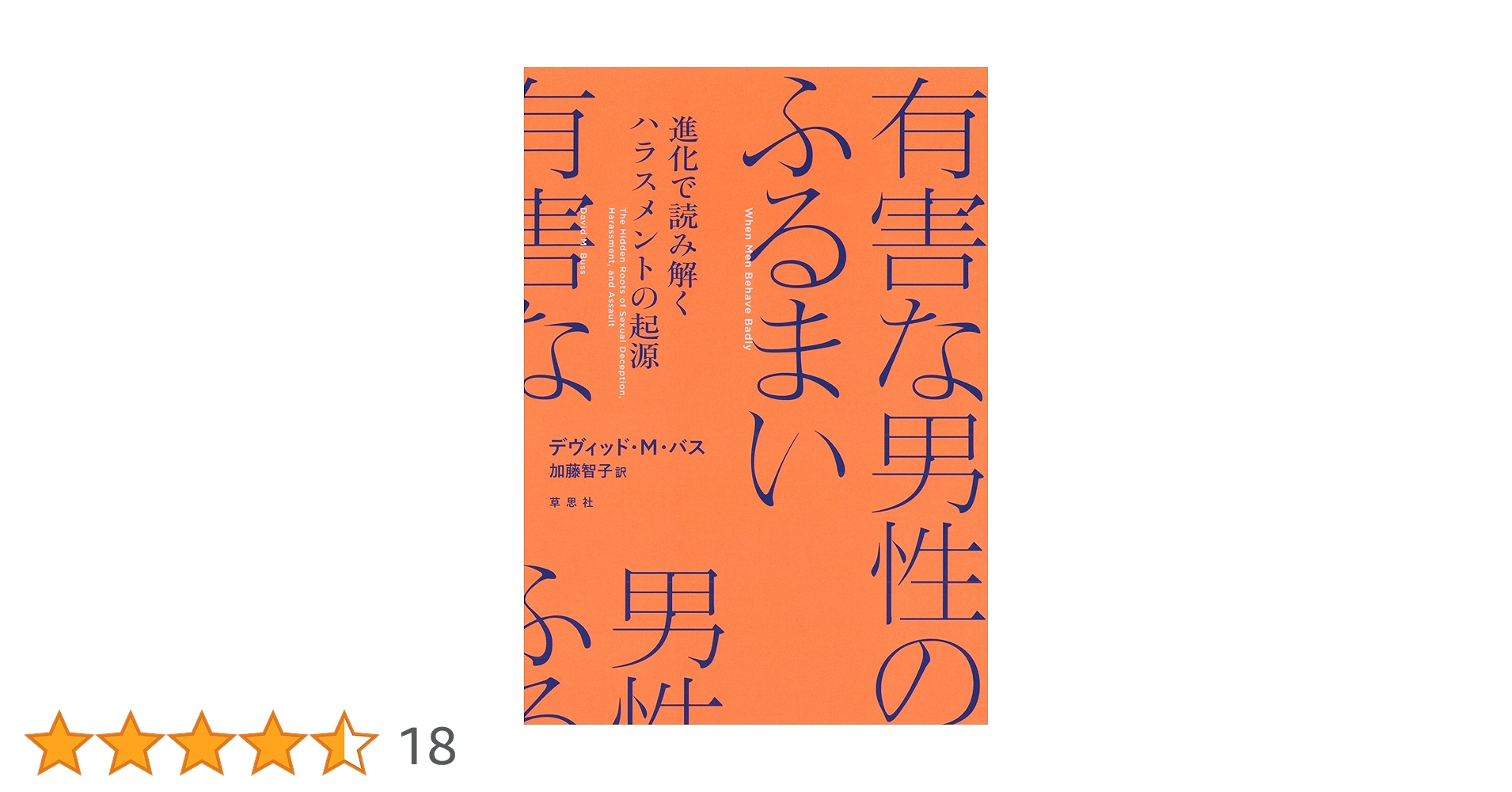
この本は、2024年7月に日本語版が刊行された比較的新しい一冊です。原著は進化心理学の第一人者であるデヴィッド・M・バスによるもので、彼は長年にわたり「人間の性行動」や「パートナー選択」に関する研究を行ってきました。
タイトルにある「有害な男性のふるまい」とは、現代社会において問題視されるハラスメントや支配的行動、暴力的な恋愛観などを指しています。著者はこれを単なる文化的な偏りや教育の失敗ではなく、「進化の過程で培われた戦略の副産物」として位置づけています。
具体的には、以下のような主張が展開されます。
- 進化心理学の視点
男性が支配や攻撃性を示すのは、生存や繁殖の競争の中で強化された戦略の一部である。 - 過去の適応が現代で問題化
狩猟採集社会や部族社会においては有効だった戦略が、現代社会では「ハラスメント」や「DV」として表面化する。 - 現代文化との接続
インターネットやSNSの普及によって、進化的な傾向が強調され、マノスフィアのような共同体で増幅される。
本書のユニークさは、こうした「厄介な行動」を道徳的に断罪するのではなく、「なぜ人間がそのような行動をとるのか」を科学的に説明しようとしている点です。
肯定的な評価
読者の中には、この本を高く評価する人が少なくありません。特に肯定的な意見として挙げられるのは以下の点です。
- 科学的裏付けがある
感情的な議論や価値観の対立ではなく、研究データや心理学的知見に基づいて説明しているため、納得感がある。 - 理解のためのツールになる
ドラマ『アドレセンス』のような作品に描かれる男性キャラクターの行動を、単に「悪い奴」と片付けずに背景を理解できる。 - 対話の出発点として有益
「男性の問題行動をどう捉えるか」という議論を感情論ではなく理論に基づいて行えるため、社会的対話を進めやすい。
特に教育者やジェンダー問題に関心を持つ研究者からは、「現場での説明材料として役立つ」という声も上がっています。
批判的な評価
一方で、本書に対して批判的な見解も存在します。
- 「進化論で正当化しているように見える」
行動の背景を進化で説明することが、結果的に「仕方ないこと」と受け取られかねない。特に加害を受ける側からは「言い訳にされる危険がある」との懸念が示されています。 - 「女性の視点が弱い」
男性の行動メカニズムに焦点が当たる一方で、被害者の心理や社会的影響についての記述が薄いという指摘も多いです。 - 「文化や環境の影響を軽視している」
進化心理学的説明は強力ですが、それだけでは文化差や歴史的背景を十分に説明できないという批判があります。
これらの意見は、本書を読む際にバランス感覚を持つ必要性を示しています。
中立的な見解
中立的な立場からは、次のような意見が目立ちます。
- 「知識として学ぶ価値はあるが、読み手の解釈次第」
- 「行動の“原因”を理解することと、“許容する”ことは別物である」
- 「ジェンダー問題を考える際の一つのレンズとして活用できる」
要するに、本書は「正解」を与える本ではなく、議論の土台を広げるための一冊であると捉えられているのです。
ドラマ『アドレセンス』との具体的な関連性
『アドレセンス』を視聴した多くの人が衝撃を受けるのは、登場人物たちが示す「有害な男性性」が決して誇張されたものではなく、現実にも存在する行動様式だからです。
ドラマでは、若い男性キャラクターが「男らしさ」を示そうとするあまり、攻撃性を強めたり、恋愛関係でパートナーをコントロールしようとしたりするシーンが描かれます。これはバスの本で解説される「進化的に形成された支配欲」と見事に重なります。
さらに、ネット空間で拡散される「女性蔑視的な発言」や「男性優位思想」もドラマの重要な要素です。これはまさに“マノスフィア”が象徴する現代的な現象であり、本書はそれを「古代から続く繁殖戦略が、現代のSNS環境で増幅されている現象」として説明してくれます。
つまり、ドラマのストーリーラインと本書の学術的な議論は相互に補完し合う関係にあり、両方を行き来することで理解が深まるのです。
口コミや評判の具体例
ここでは、読者の反応をより具体的に整理してみましょう。
肯定的な口コミ
- 「この本を読んで初めて、“男らしさ”という概念が単なる文化的な押し付けではなく、進化の歴史の中で形づくられてきたと理解できた。ドラマのキャラクターがなぜあんな行動をとるのか、少し腑に落ちた」
- 「性差別やハラスメントを擁護するための本ではなく、むしろ“なぜ起こるのか”を説明することで予防策を考えられる。教育現場で役立ちそう」
批判的な口コミ
- 「読んでいて不快感もあった。科学的説明といっても、加害を受ける側からすれば“だから仕方ない”と言われているように感じる」
- 「女性の体験談や被害者の視点がもっと入っていればバランスが取れたはず。男性側の心理ばかりに偏っている」
中立的な口コミ
- 「本書は事実を提示しているが、どう解釈するかは読み手に委ねられている。危うさもあるが、議論のきっかけにはなる」
このように、読者の立場や問題意識によって受け止め方が大きく変わるのが特徴です。
この本を読むメリット
- 背景理解が深まる
ドラマのようなフィクションをより深いレベルで理解できる。単なる物語ではなく、現実社会との接点が見えてくる。 - 対話の出発点になる
有害な男性性について、感情的な批判や単純な善悪ではなく、科学的に議論を始めることができる。 - 自己理解につながる
男性読者にとっては、自分の行動や感情の根源を見つめ直すきっかけになる。女性読者にとっては、相手の行動を「理解」するツールになる。
読む際の注意点
一方で、本書を手に取る際には注意すべき点もあります。
- 免罪符にしないこと
「進化がそうさせているから仕方ない」という使い方は危険。本書の目的は理解であって正当化ではありません。 - 視点の偏りを認識する
男性の行動原理に焦点を当てているため、女性の体験や社会的構造については他の文献で補う必要があります。 - 複数の視点を持つ
本書だけで「男性性」を語ろうとせず、社会学やフェミニズム、臨床心理学など他分野の知見と組み合わせることでバランスがとれます。
おすすめする人/しない人
おすすめする人
- 『アドレセンス』を見て、登場人物の行動の背景をもっと深く理解したい人
- ジェンダー問題に関心があり、感情論を超えた議論の材料を探している人
- 教育現場やカウンセリングで、男性の攻撃性や支配欲の背景を説明する必要がある人
おすすめしない人
- 「有害な男性性」を糾弾したいだけの人(本書は断罪的ではないため物足りなく感じる可能性が高い)
- 学術的な議論よりも被害者の声や具体的なケーススタディを重視する人
- 読んでいて不快になる可能性を避けたい人
ドラマと本を組み合わせて考える意義
『アドレセンス』はフィクションですが、現実社会の問題を濃縮して描き出しています。一方で、『有害な男性のふるまい』は科学的アプローチからその現実を説明しています。両者を組み合わせて考えることで、私たちは次のような理解を得ることができます。
- 物語を通して感情的に共感し、本を通して理論的に理解する
- 登場人物を“異常”と見るのではなく、“人類の歴史的背景”の中に位置づける
- 未来に向けて、どうすればより健全な関係を築けるのか考えるきっかけになる
この相互作用こそが、フィクションと学術書を往復する大きな意義といえるでしょう。
まとめ
Netflixドラマ『アドレセンス』は、有害な男性性やマノスフィアといった現代的テーマを真正面から描いた挑戦的な作品です。視聴後に心に残る不安や疑問を解消する手がかりとして、デヴィッド・M・バスの『有害な男性のふるまい: 進化で読み解くハラスメントの起源』は非常に有益です。
もちろん本書は賛否を呼ぶ一冊であり、読み方を誤れば「免罪符」として利用されてしまう危険もあります。しかし、正しく読み解けば、ドラマの背後に潜む現実的な問題を理解するための強力なツールとなります。
『アドレセンス』と本書を行き来しながら読むことで、フィクションを超えた社会的理解が得られ、日常の人間関係や社会問題に対してもより深い洞察を持つことができるでしょう。