ADHDに関する本は数多く出版されていますが、対象読者や目的によって「役立つ一冊」は大きく異なります。本記事では、ADHD当事者として自己理解を深めたい方、家族やパートナーとして支え方を学びたい方、教育や支援に関わる立場で実践的な知識を得たい方に向けて、信頼できる6冊を厳選しました。それぞれの特徴と口コミ、そしてどの立場に最もおすすめできるかを整理した比較表も用意しています。ADHDを「弱点」ではなく「特性」として捉え直し、前向きに共生していくための読書ガイドとしてご活用ください。
ADHDの僕が苦手とされる事務にとことん向き合ってみた。
- 著者:小鳥遊
- 発売年月:2025年7月24日

概要
本書は「ADHD×事務」という一見もっとも相性の悪い領域にあえて正面から挑んだ一冊です。著者自身の当事者経験を軸に、抜け漏れ・先送り・ケアレスミスといった典型的な困りごとをどのように仕組みで補うかが具体的に描かれています。「事務=地味な作業」ではなく「現実を進めるプロセス」と再定義し、誰にとっても避けて通れない基盤を整える実践的な方法論が展開されています。
主な口コミ・評判
肯定的な意見
- 「読みやすく一気に読めた」「頭にすっと入ってくる」という声が多く、ADHDの特性を考慮した構成や文章の平易さが高評価を得ています。
- 「できる人の当たり前を分解して、再現可能にしている」と評価され、タスクを小さく分け、日付や手がかりを添えて仕組みに落とし込む工夫が支持されています。
中間的な意見
- 「当事者のリアルな困りごとが書かれているので机上の空論にならない」という一方で、対象が“事務作業”に集中しているため、クリエイティブ職や現場作業中心の人は応用に工夫が必要とする声もあります。
- 「仕事が苦手な人のあるある事例と解決策が良かった」との意見もありつつ、実用性の評価は読者の環境によって分かれる傾向があります。
批判的な意見
- 「要は“分解すればいい”という単純な話では?」と感じる読者もおり、基礎的な方法に物足りなさを覚える声も一部あります。
評判の背景を深掘り
この本が評価される最大の理由は「自分を変えるのではなく、仕組みを変える」という視点です。手順の細分化、外部化(見える化や日付化)、責任の配線替えといった工夫が、集中力や気分の波に左右されやすいADHD当事者でも継続しやすい仕組みを実現します。一方、既に高度なタスク管理を実践している人や、医療的・制度的な知識を深めたい読者にとっては射程外に感じられる部分もあります。
なぜおすすめなのか
本書の価値は「事務=誰もが避けられない現実処理」を、ADHD特性を持つ人でも扱いやすい仕組みに翻訳している点にあります。当事者にとっては自己否定を減らしながら日常を前進させる実装可能な方法を、家族や職場の人にとっては“なぜ事務でつまずくのか”を理解する手がかりを提供します。基盤的な実務スキルを支える一冊として、初めてADHDの仕事のつまずきを整理したい人に特に勧められる内容です。
「大人のADHD」のための段取り力
- 監修:司馬理英子
- 発売年月:2016年1月13日

概要
本書は、大人のADHDに特有の「段取りの難しさ」に焦点を当て、時間管理・モノの管理・プランニング・記憶補強・持続力といった5つのテーマを具体的に解説しています。イラストや図解を多用し、抽象的な「注意力の課題」を日常生活や仕事の現場に即した行動レベルに落とし込んでいる点が特徴です。
また、単なる「気合い」や「根性」ではなく、行動を支える仕組みやツールを使う実践的アプローチを示しており、ADHDの人が自分に合った段取りのスタイルを見つけるための実用書といえます。
主な口コミ・評判
肯定的な意見
- 「イラストが多くて直感的に理解できる」「要点が整理されていて頭に入りやすい」と、構成のわかりやすさが評価されています。
- ADHDの傾向を持つ人だけでなく、「片付けが苦手」「締切に追われがち」といった一般的な悩みを持つ人にも役立つとの声があります。
- 職場や家庭で具体的にどう行動すれば良いかが書かれているため、実践に直結しやすいと好評です。
中間的な意見
- 内容がやや入門的で「すでに自己管理法を試してきた人には物足りない」という意見も見られます。
- ADHDを医学的・脳科学的に深く知りたい人には不十分とされる一方、「生活の工夫が欲しい人」には向いているとの評価があります。
批判的な意見
- 「知識としては平易すぎる」「具体例が一般的すぎて自分の状況に当てはめにくい」との指摘があります。
- 医師監修という安心感はあるものの、専門的な治療指針を期待するとギャップを感じる読者もいます。
評判の背景を深掘り
本書が高く評価されるのは、難しい心理学や医学の説明を避け、日常生活の中で実際に役立つ工夫をわかりやすく提示している点です。
一方で、すでにADHDの支援書や自己管理法を読み込んでいる人にとっては、既知の内容が多く感じられる場合があります。つまり、「初めて段取り改善に取り組む人」に最適化されているともいえます。
なぜおすすめなのか
「段取り」はADHDにおいて最も大きなつまずきのひとつであり、それを体系的に整理した実用書は多くありません。本書は、家庭・職場・学習のあらゆる場面で生じる課題を具体的な方法に置き換えることで、「今日から試せる」工夫を提供しています。
専門的な治療書ではなく、生活に寄り添った“実用ハンドブック”として、ADHDの本人はもちろん、パートナーや支援者にも理解を深める一冊として推奨できます。
ADHDの夫を責める前に読む本:べきねば妻歴15年で身につけた失敗からのしなやかさ
- 著者:あろはる
- 発売年月:2024年1月26日
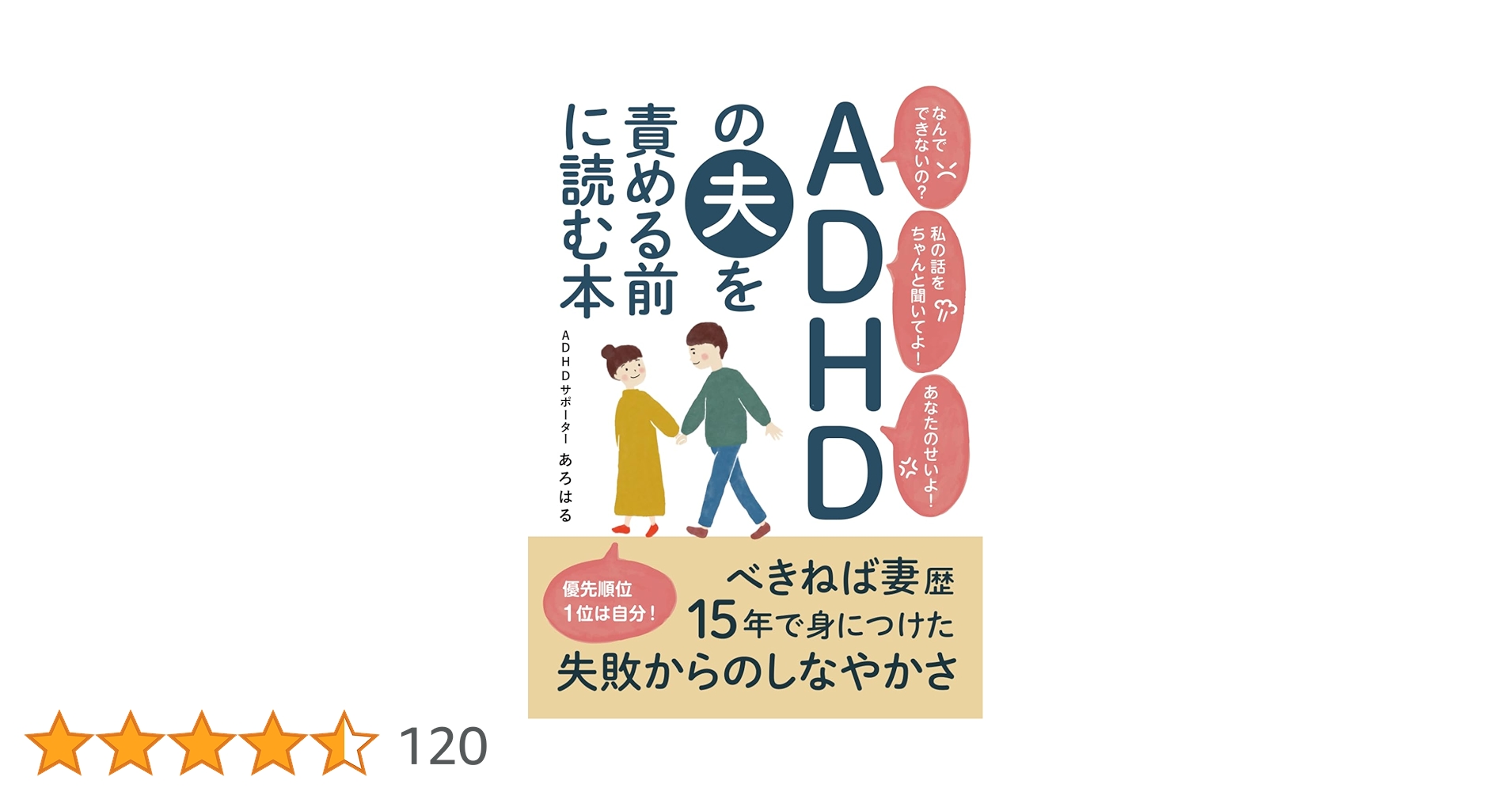
概要
本書は、ADHDの特性をもつ夫と15年以上生活を共にしてきた著者が、自身の経験から得た知恵をまとめた体験的エッセイ兼実践書です。テーマは「責める」ではなく「理解する」。家事の抜け漏れ、感情の波、衝動性など、日常生活で繰り返される摩擦を、どのように受け止め、しなやかに付き合っていくかが語られます。
著者は「べき・ねば」に縛られて夫を責め続けてしまった過去を振り返り、そこから脱却するための思考転換や具体的な関わり方を紹介しています。家庭という場において、パートナーシップを壊さずにADHDと共存するための視点を提供しているのが特徴です。
主な口コミ・評判
肯定的な意見
- 「同じ悩みを抱える妻として共感できる」「救われた気持ちになった」と、当事者家族からの共感の声が目立ちます。
- 専門書のように難しい言葉ではなく、日常生活の具体的エピソードから学べるため、読みやすいと評価されています。
- 「責める」から「理解する」へと気持ちを切り替えるきっかけになったというレビューもあります。
中間的な意見
- 「体験談中心で専門的な知識や科学的解説は少ない」との声もあり、知識を深めたい人にはやや物足りなさを感じる場合があるようです。
- ADHD当事者本人よりも、配偶者や家族に向けた内容なので、読む立場によって実用度が変わるという意見も見られます。
批判的な意見
- 「結局は家庭ごとの事情に依存するため、再現性が低い」という指摘があります。
- 問題解決というより“考え方の切り替え”が中心のため、実践的な解決法を期待するとギャップを感じる読者もいます。
評判の背景を深掘り
評価が高いのは、ADHDの専門家や医師ではなく、同じ立場に立つ「妻」という当事者目線で語られている点です。机上の理論ではなく「リアルな生活感」に根ざしているため、同じ境遇の読者に深く刺さりやすい一方で、汎用的な知識や対処法を求める読者には不足を感じさせる構成ともいえます。
また「失敗談をあえてさらけ出している」という誠実さが共感を呼んでいるのも特徴です。
なぜおすすめなのか
ADHDに関する本は本人向けや医学的解説書が多い中で、配偶者・家族に焦点を当てた書籍は少数派です。本書は、夫婦関係の摩擦をどう乗り越えるかを「妻の視点」から描くことで、支える側の苦しみや工夫をリアルに伝えています。
ADHD本人が読むことでパートナーの気持ちを理解する助けになり、配偶者が読むことで「責める」以外の対応を学べる一冊です。家庭の中でADHDを理解し、共に歩むための“伴走書”として強く推奨できます。
「忘れっぽい」「すぐ怒る」「他人の影響をうけやすい」etc. ADHDコンプレックスのための“脳番地トレーニング”
- 著者:加藤俊徳
- 発売年月:2020年7月7日
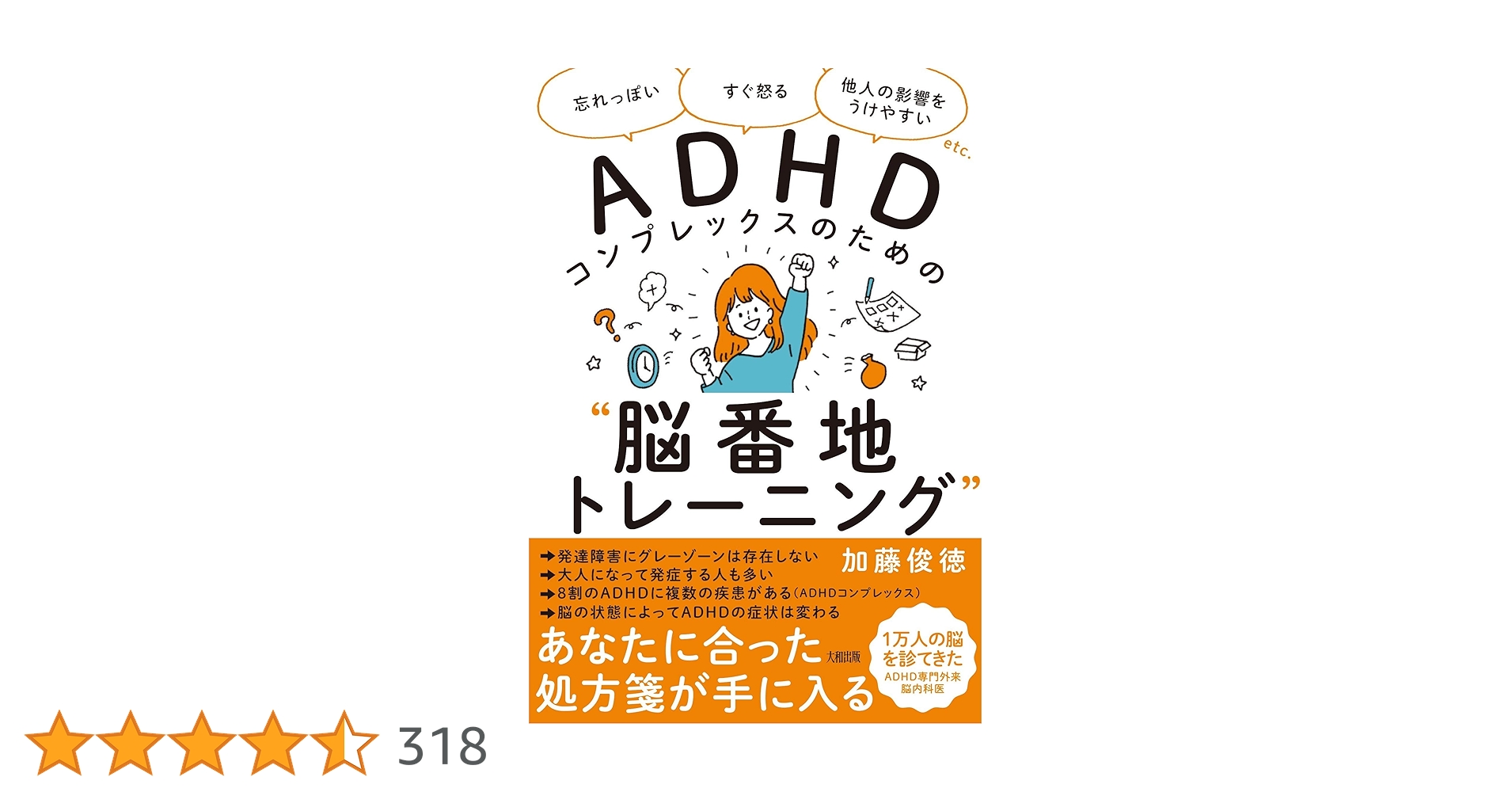
概要
本書は、脳科学者である加藤俊徳氏が提唱する「脳番地理論」をベースに、ADHDに見られる特徴的な困りごとにアプローチする実践的トレーニング集です。忘れ物が多い、感情が爆発しやすい、他人の影響を受けやすい――こうした日常的な“ADHDあるある”を、脳の機能ネットワークを強化するトレーニングで改善しようという試みです。
脳を「思考系」「感情系」「記憶系」「伝達系」など複数の“番地”に分け、それぞれを意識的に鍛えることで弱点を補い、強みを引き出す方法が解説されています。専門的な脳科学を土台にしつつ、家庭や職場で手軽にできるワークが豊富に盛り込まれているのが特徴です。
主な口コミ・評判
肯定的な意見
- 「イラストや図が多くて理解しやすい」「すぐに実践できるトレーニングが紹介されていて役立った」との声が多いです。
- ADHDの症状を“性格”ではなく“脳の使い方の偏り”と捉え直すことで、自己否定感が和らいだという感想もあります。
- 子どもから大人まで幅広く使える内容で、親子で一緒に取り組める点も評価されています。
中間的な意見
- 「脳番地」という独自の理論に基づいているため、医学的エビデンスを重視する読者にはやや物足りないと感じられることがあります。
- 脳科学の入門的な知識と実践法の橋渡し的な内容なので、「根拠よりも実践法を知りたい人」には向いているが、学術的に深掘りしたい人には合わないという意見もあります。
批判的な意見
- 「紹介されているトレーニングが一般的な生活習慣改善や脳トレに近く、特別感に欠ける」との指摘があります。
- ADHDの改善を大きく期待すると、効果が実感できずに失望する可能性もあるという声も見られます。
評判の背景を深掘り
高く評価されるのは、抽象的な「脳科学」を日常に落とし込み、誰でも取り組める形に翻訳している点です。忘れっぽさや感情の起伏を「自分の意志の弱さ」ではなく「脳の使い方の偏り」と理解できるため、読者に安心感と自己受容をもたらします。
一方で、“脳番地”という理論そのものは著者独自のフレームであるため、エビデンスを重視する人からは「科学的裏付けが薄い」と評価が割れる傾向があります。
なぜおすすめなのか
ADHDを「脳の特性」として捉え直し、訓練によって改善や補強が可能であることを示す点が本書の強みです。心理的な自己肯定感を高めながら、具体的な改善行動に移せるため、本人はもちろん、子どもを支援する親にとっても有益です。
専門書より実用書に近い構成なので、「まず自分でできることから始めたい」「日常生活で取り入れやすい工夫が知りたい」という人にとって最初の一冊としておすすめできます。
ADHD2.0 特性をパワーに変える科学的な方法
- 著者:エドワード・M・ハロウェル、ジョン・J・レイティ
- 監修:榊原洋一
- 翻訳:橘陽子
- 発売年月:2023年9月21日
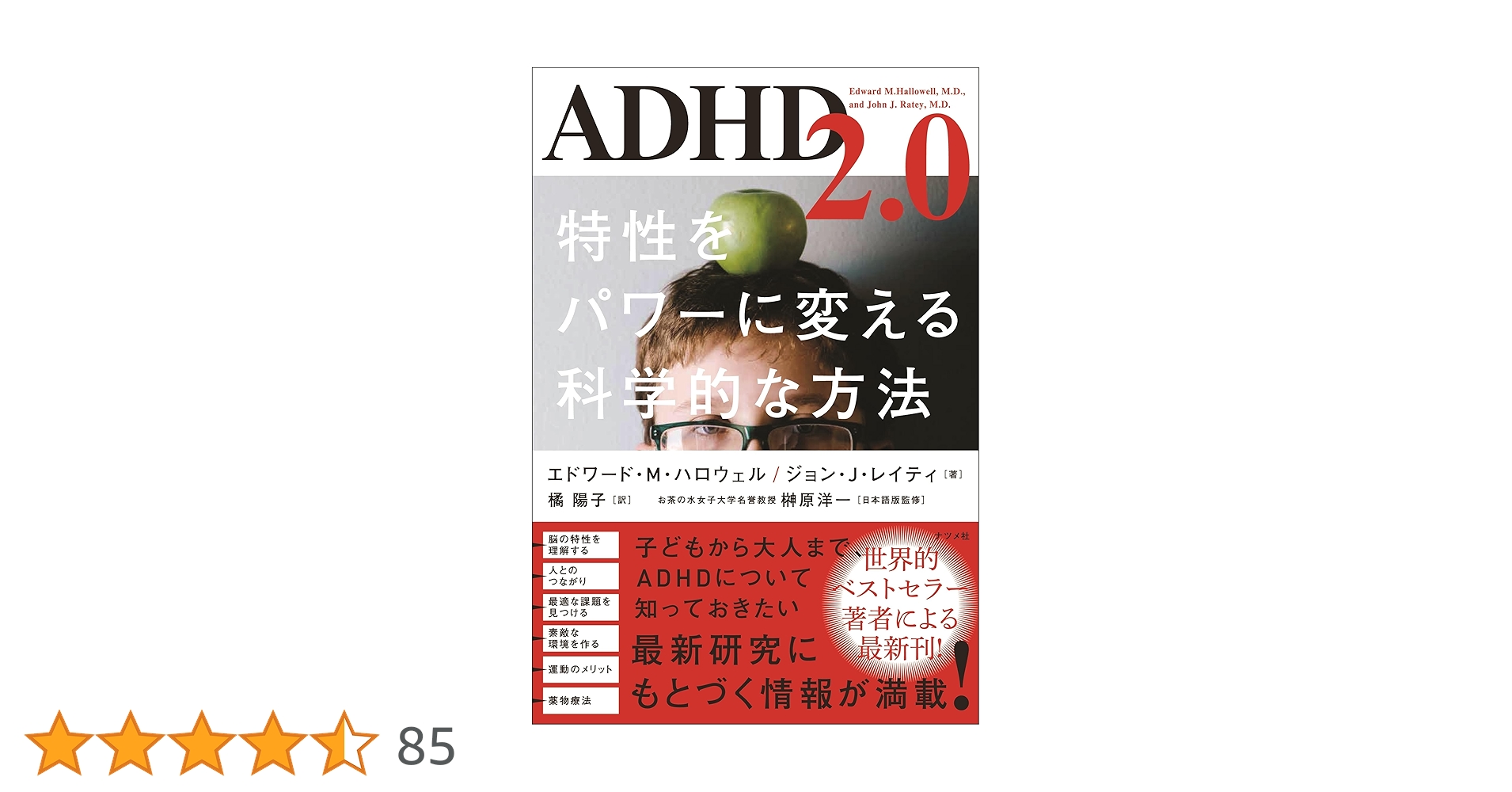
概要
本書は、ADHD研究の第一人者であるハロウェル医師とレイティ医師が提唱する「ADHD2.0」という新しい捉え方を解説した一冊です。従来、ADHDは「欠陥」や「障害」と見なされがちでしたが、本書では「特性」として再定義し、そのエネルギーを創造性や集中力の源に変えていくことを目的としています。
内容は、脳科学の最新知見と臨床の実例を交えながら、ADHD特性を活かす具体的な方法を紹介。環境をどう整えるか、人間関係をどう築くか、集中力の波をどう味方につけるかなど、生活全般に応用できるヒントが詰まっています。
主な口コミ・評判
肯定的な意見
- 「ADHDをポジティブに捉える視点が新鮮」「欠点だと思っていたことを強みにできると勇気づけられた」といった前向きな感想が目立ちます。
- 世界的に著名な専門家による実例と研究データが紹介されており、安心感や説得力があるとの声があります。
- 自己啓発的な要素も含まれているため、読後に「自分の特性を活かしてみよう」という行動意欲が高まったという評価も見られます。
中間的な意見
- 内容はわかりやすいが、「科学的知見よりも精神的支えとしての要素が強い」と感じる読者もいます。
- すでにADHDに関する複数の専門書を読んでいる人にとっては、目新しさよりも「再整理された解釈」として受け取られるケースもあります。
批判的な意見
- 「楽観的すぎる」「ADHDの困難を軽視しているのではないか」と指摘する声もあります。
- 実用的な細かいノウハウを期待すると、「抽象的な励ましに偏っている」と感じる人もいるようです。
評判の背景を深掘り
高い評価を受ける理由は、ADHDを“できないこと”の集まりとして語るのではなく、“才能や強みを引き出す資源”として位置づけた点です。このポジティブな切り口が、多くの当事者や家族に希望を与えています。
ただし、具体的な行動マニュアルというよりは「考え方の枠組み」を提示する色合いが強いため、すぐに実践したい読者には物足りなく映る可能性があります。
なぜおすすめなのか
ADHDに関する従来の本は、症状や対処法に焦点を当てた「問題解決型」が多いのに対し、本書は「特性を資源としてどう活かすか」という発想転換を提供します。専門家による裏付けと、実生活での応用可能性を兼ね備えているため、ADHDを「弱点」としてしか見られなかった人に、新しい視点と自己受容の力を与えてくれる一冊です。
本人はもちろん、家族や支援者にとっても「ADHDを肯定的に理解する」ための入門書としておすすめできます。
最新図解 ADHDの子どもたちをサポートする本
- 著者:榊原洋一
- 発売年月:2019年2月12日

概要
本書は、小児発達の第一人者である榊原洋一氏が、ADHDの子どもを理解し支援するために執筆した実用的なガイドブックです。豊富なイラストと図解を用いて、ADHDの特性、診断、日常生活での困りごと、医療や学校での対応などをわかりやすく解説しています。
薬物療法や行動療法、ペアレントトレーニングといった治療法の基礎知識に加え、家庭や学校で直面する「忘れ物が多い」「集中が続かない」「友達関係がうまくいかない」といった具体的な課題へのサポート方法が、ケースごとに紹介されています。子ども本人だけでなく、親や教師がどう寄り添うかに焦点を当てているのが特徴です。
主な口コミ・評判
肯定的な意見
- 「図解が多く、とてもわかりやすい」「専門的な内容を一般向けにかみ砕いていて助かった」といった評価が目立ちます。
- 子どもの日常生活の事例が豊富に盛り込まれており、「自分の子どもにそのまま当てはまった」「すぐに実践できた」という声があります。
- 医師が著者であるため、信頼感があると支持されています。
中間的な意見
- 「内容は広く浅くまとまっているため、さらに深い専門知識を求める人には物足りない」という感想もあります。
- ADHDに初めて触れる保護者や教師には役立つが、すでに支援の実務に関わっている専門職にとっては基礎知識の確認に留まるという指摘も見られます。
批判的な意見
- 「一般向けすぎて実践の深さが足りない」「治療や支援の詳細なマニュアルを期待すると不満が残る」という意見も一部あります。
- また、薬物療法の説明がシンプルにまとめられているため、具体的な副作用や処方判断などを知りたい人には不足と感じられるケースもあります。
評判の背景を深掘り
本書が評価される理由は、専門的な医学知識を持たない保護者や教育者でもすぐに理解できる構成にあります。「専門書と実用書の中間」に位置づけられ、導入書としての価値が高いのが特徴です。一方で、深い専門知識や詳細な支援ノウハウを求める人には物足りなく映るため、評価は読者層によって分かれる傾向があります。
なぜおすすめなのか
ADHDに関する子ども向けの本は多くありますが、本書は 図解・ケース別対応・家庭と学校の双方の視点 を兼ね備えている点でユニークです。親や教師がすぐに実践できる工夫を提示しつつ、医療機関にかかる際の基礎知識も整理されているため、入門書として最適です。
特に「子どもを理解し、サポートしたいが、何から始めればいいかわからない」という人に強くおすすめできる一冊です。
ADHD関連書籍の比較表(対象別おすすめ分類)
| 番号 | 書名 | 著者/監修 | 発売年月 | 主な対象読者 | 特徴・おすすめポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADHDの僕が苦手とされる事務にとことん向き合ってみた。 | 小鳥遊 | 2025/7/24 | 本人向け | ADHD当事者が「事務作業」という苦手領域に挑戦した実録。タスク分解・仕組み化の実践例が多く、仕事でつまずきやすい人に最適。 |
| 2 | 「大人のADHD」のための段取り力 | 司馬理英子(監修) | 2016/1/13 | 本人向け・支援者向け | 時間管理・モノの管理など5つのテーマで段取り力を解説。イラスト多めで初学者でも理解しやすい。支援者にも日常的な工夫の理解に役立つ。 |
| 3 | ADHDの夫を責める前に読む本 | あろはる | 2024/1/26 | 家族・パートナー向け | 著者の体験談を基に、夫婦関係の中でADHDを理解する視点を提示。責めるより理解する姿勢を学べる。 |
| 4 | ADHDコンプレックスのための“脳番地トレーニング” | 加藤俊徳 | 2020/7/7 | 本人向け・親子向け | 脳科学に基づくトレーニング法。日常生活でできる実践法が豊富で、子どもから大人まで幅広く使える。 |
| 5 | ADHD2.0 特性をパワーに変える科学的な方法 | ハロウェル/レイティ(著) 榊原洋一(監修) 橘陽子(翻訳) | 2023/9/21 | 本人向け・家族向け | ADHDを「弱点」から「強み」へと再定義。前向きな視点を与える国際的ベストセラー。自己受容や家族の理解に役立つ。 |
| 6 | 最新図解 ADHDの子どもたちをサポートする本 | 榊原洋一 | 2019/2/12 | 支援者・家族向け | 子どものADHD支援に特化。家庭・学校・医療のケース別対応を図解でわかりやすく解説。親や教師の入門書として最適。 |
まとめ
- 本人向け:①、②、④、⑤
→ 自己理解や生活改善に役立ち、タスク管理・ポジティブな視点・脳科学的アプローチと多角的に選べる。 - 家族・パートナー向け:③、⑤、⑥
→ 特に③は妻の視点から書かれており、家族関係の改善に直結。⑤は特性を肯定的に捉える視点を共有できる。⑥は子どもの支援に必読。 - 支援者向け:②、⑥
→ 教師・医療従事者・職場の同僚など、当事者をサポートする立場の人が理解を深めやすい構成。

