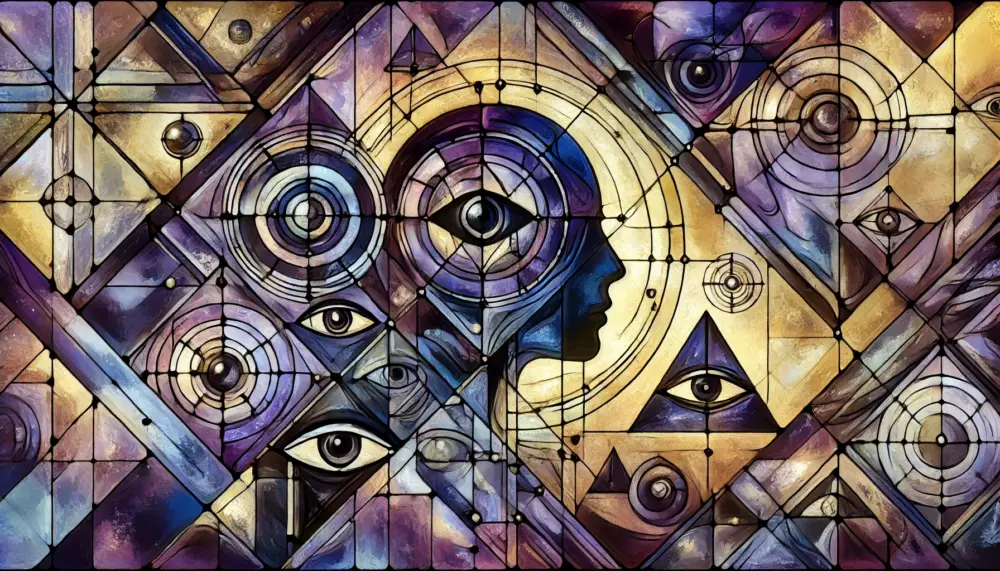陰謀論は、今や一部の人々の特殊な思考ではなく、SNSやメディアを通じて私たちの日常に影響を与える身近な現象となっています。政治的分断、社会的不安、さらには国際的な情報戦にも結びつく陰謀論を理解することは、現代を生きる上で避けられない課題です。この記事では、日本と海外の研究者やジャーナリストが執筆した8冊の注目書籍を取り上げ、それぞれの特徴や評判を整理しました。入門的に学びたい人から、学術的・国際的な視点で深く掘り下げたい人まで、目的に応じた一冊を見つける参考にしてください。
となりの陰謀論
著者:烏谷昌幸|発売年月:2025年6月
概要(どんな本?)
本書は、慶應義塾大学の政治コミュニケーション研究者である著者が、陰謀論を「特殊な人々の異常な思考」ではなく、私たちの生活のすぐ隣に存在する身近な現象として捉え直す試みです。SNS時代に拡大する「パラレルワールド(現実の二重化)」という視点を手がかりに、Qアノンや米大統領選挙の不正説などを事例に、人々が陰謀論に惹かれる心理や、その社会的な影響を体系的に解説しています。構成は「陰謀論とは何か」から始まり、「パラレルワールド」「陰謀論政治」「過小評価の危うさ」へと展開し、入門としても読みやすい設計になっています。
本書のねらいと構成(要点)
- 陰謀論の定義と輪郭:偶然を「誰かの意図」として解釈する人間の思考傾向を整理。
- “パラレルワールド”化:同じ現実を見ながら異なる世界観が併存するSNS時代の情報環境を解説。
- 陰謀論政治:トランプ現象やQアノンを例に、政治と陰謀論の結びつきを分析。
- 過小評価の危険:陰謀論を「愚かな少数者の思考」と軽視することが社会全体のリスクにつながることを指摘。
主な口コミ・評判(深掘り)
肯定的評価
- 読みやすく整理されており、専門知識がなくても理解しやすい。
- 陰謀論を「人間の自然な欲望」として扱う視点が新鮮で、自分自身の思考も振り返れる。
- 現代のSNSや情報空間を分析する上で非常にタイムリーで実用的だと評価されている。
中間評価
- 心理学的な実験や学術的な深掘りは少なく、事例紹介が中心に感じられるとの声。
- 専門的研究書というより「入門新書」としての位置づけを理解したうえで読むのが良い。
批判的評価
- 米国事例の比重が大きく、日本社会の具体的な陰謀論についてもっと掘り下げて欲しかったという指摘。
- 陰謀論に対する具体的な解決策や予防策を期待した読者にはやや物足りない部分がある。
専門的に見た読みどころ
- 「パラレルワールド」概念は、SNSのアルゴリズムが異なる現実を作り出す仕組みを説明する上で極めて有効。
- 「奪われ感」と政治の関係は、ポピュリズムや分断の理解に直結し、日本の社会状況を読み解く際にも応用可能。
- 「私たち自身の問題」としての陰謀論という視点は、情報リテラシー教育や社会的対策の出発点となる。
こんな読者におすすめ
- 陰謀論について基礎から体系的に学びたい人。
- 学校教育や研修で情報リテラシーを扱う教育関係者。
- 現代社会の分断や政治コミュニケーションを理解したいビジネスパーソンや研究者。
陰謀論はなぜ生まれるのか Qアノンとソーシャルメディア
著者:マイク・ロスチャイルド|翻訳:烏谷昌幸、昇亜美子|発売年月:2023年

概要(どんな本?)
本書は、アメリカで実際に広がった「Qアノン」という巨大な陰謀論を徹底的に追跡・分析した著作です。著者マイク・ロスチャイルドは米国のジャーナリストであり、長年にわたり陰謀論とデマの研究・取材を行ってきました。彼は「Qアノン」がどのように生まれ、ネット掲示板からSNSへと拡散し、やがて米国社会や政治に深刻な影響を与えたのかを丹念に描き出します。翻訳は日本の陰謀論研究者である烏谷昌幸らが手がけ、日本の読者にも読みやすく整理されています。
本書のねらいと構成(要点)
- 発生のプロセス:匿名掲示板4chanや8chanから始まった「Qの投稿」が、いかにしてカルト的ムーブメントへ発展したかを解説。
- SNSの拡散力:FacebookやTwitter(現X)が、無根拠な陰謀説をどのように広範に広めたかを具体的に描写。
- 人が惹かれる心理:不安や孤独、世界を単純化して理解したいという欲求が陰謀論の土壌になることを指摘。
- 政治への浸透:トランプ前大統領を救世主視する言説や、議会襲撃事件など、民主主義を揺るがした実例を分析。
主な口コミ・評判(深掘り)
肯定的評価
- 「Qアノンの全体像を把握できる“決定版”のような本」と評され、研究者やジャーナリストからも高く評価。
- 陰謀論の裏側に潜む人間心理を冷静に解き明かす筆致が読みやすいとの声が多い。
- 日本語版では翻訳が丁寧で、原著の情報量を損なわずに整理されていると好評。
中間評価
- アメリカ事例に比重があるため、日本国内の陰謀論事情を知りたい読者には物足りない部分もある。
- 専門用語や海外事情に不慣れな読者にとっては、理解にやや時間がかかるとの声。
批判的評価
- 著者がジャーナリストであるため、学術的な分析よりもルポルタージュ的な要素が強いと指摘する読者もいる。
- 「なぜ信じるのか」の心理面にもっと焦点を当ててほしかったという声もある。
専門的に見た読みどころ
- 「Qアノン」の生成過程を詳細に追跡しており、デマや陰謀論がいかにして「社会運動」に変貌するかを理解できる。
- SNSプラットフォームの役割に着目しており、現代の情報空間を考える上で重要なケーススタディ。
- 心理と政治の接合点を可視化しているため、陰謀論が単なる「妄想」ではなく「政治的武器」となりうることを示す。
こんな読者におすすめ
- 陰謀論がどのように現代社会に広がるのかを、米国の事例から学びたい人。
- SNS時代の情報拡散やフェイクニュースの危険性を研究・教育に活かしたい人。
- Qアノンを中心に、現代の陰謀論文化を総合的に理解したい人。
陰謀論-民主主義を揺るがすメカニズム
著者:秦 正樹|発売年月:2022年10月20日
概要(どんな本?)
本書は、陰謀論が「なぜ広がるのか」「なぜ人々が信じてしまうのか」、そしてそれが民主主義の基盤をどのように揺るがすのかを解き明かす研究書です。著者は社会心理学・政治学の観点から、デマやフェイクニュースの流通構造を分析し、陰謀論が単なる誤情報ではなく「社会を動かす力」を持つことを示しています。特にSNSを中心に拡散する情報の仕組みや、人々の不安・不信感がどのように動員されるかを多角的に解説しています。
本書のねらいと構成(要点)
- 陰謀論の構造:偶然や不確実な出来事を「誰かの意図」として解釈してしまう認知のメカニズムを整理。
- 拡散の仕組み:ネットワーク上での情報流通やアルゴリズムの働きによって、誤情報がいかに強化されるかを分析。
- 政治への影響:選挙や世論形成において陰謀論が利用される過程を事例とともに解説。
- 民主主義のリスク:陰謀論が社会の信頼を破壊し、分断や過激化をもたらす危険性を論じる。
主な口コミ・評判(深掘り)
肯定的評価
- 「陰謀論を心理・社会・政治の三方向から整理しており、非常に体系的」と評価する声が多い。
- 「社会不安や格差といった背景まで踏み込んでいる点が秀逸」と専門家からも支持。
- 入門書というよりも分析的な内容で、学術的な裏付けを求める読者に好評。
中間評価
- 構成は丁寧だが専門的であり、「気軽に読む入門書」というよりはやや硬質。一般読者には難解に感じられるとの声もある。
- 海外事例の比重が高く、日本国内の具体的な事例をもっと知りたかったという意見。
批判的評価
- 学術的な引用が多いため、研究バックグラウンドがない読者には「読みにくい」との印象もある。
- 「解決策の提示が少なく、問題提起にとどまっている」とする批判もある。
専門的に見た読みどころ
- 心理学と政治学を架橋:人が陰謀論を信じる心理メカニズムを、社会的影響力や政治動員と接続。
- アルゴリズム批判の視点:SNSによる情報の増幅効果を、学術的に整理している。
- 民主主義の脆弱性:陰謀論が「民主的議論の前提となる事実認識」を崩壊させる点を明確に描いている。
こんな読者におすすめ
- 陰謀論を社会心理学と政治学の両面から理解したい人。
- 学術的な分析や理論的な整理を求める研究者や学生。
- SNS時代の情報空間と民主主義のリスクを深く考えたい読者。
社会分断と陰謀論 虚偽情報があふれる時代の解毒剤
著者:雨宮 純、烏谷 昌幸、長迫 智子、上野 庸平、岡部 友樹|発売年月:2025年5月15日
概要(どんな本?)
本書は、急速に拡大する陰謀論と偽情報が社会に及ぼす影響を、複数の研究者が協働で分析した最新の学術的成果をまとめたものです。タイトルにある「解毒剤」という言葉が象徴するように、単なる陰謀論批判にとどまらず、社会を分断から回復させるための具体的な処方箋を提示する点が特徴です。SNSやYouTubeなどでの偽情報拡散、日本社会における事例、国際的な潮流などを横断的に扱い、「なぜ人は陰謀論に惹かれるのか」という心理的要因から、「どうすれば誤情報に対抗できるのか」までを包括的に論じています。
本書のねらいと構成(要点)
- 陰謀論と分断の関係:虚偽情報が分断を固定化・拡大するメカニズムを解説。
- 心理と行動科学の知見:人々が陰謀論に陥る要因を、認知バイアスや集団心理から説明。
- 日本社会における事例:コロナ禍で拡散した陰謀論や反ワクチン運動をケーススタディとして分析。
- 解毒剤としての対策:メディアリテラシー教育、制度的な仕組み、個人レベルでの情報との向き合い方を提案。
- 複数著者による多角的視点:政治学・社会心理学・メディア研究の専門家が、それぞれの立場から論じている。
主な口コミ・評判(深掘り)
肯定的評価
- 「複数の専門家による共同研究で、幅広い視点が得られる」と専門性の高さが評価されている。
- 「批判だけでなく**“解毒剤”という前向きな提案がある点が新鮮**」との声。
- 日本国内の具体的事例を扱っているため、「海外本よりも身近で理解しやすい」という感想が目立つ。
中間評価
- 内容が多角的である反面、テーマごとの掘り下げが浅いと感じる読者もいる。
- 複数著者による構成のため、章ごとに文体やアプローチが異なり、読みやすさにばらつきがあるとの意見。
批判的評価
- 「陰謀論に対抗する実践的手法について、もう一歩踏み込んだ議論が欲しかった」という指摘。
- 学術的知見を一般向けに翻訳する工夫がやや不足しており、難解に感じる読者もいる。
専門的に見た読みどころ
- 学際的アプローチ:社会心理学、政治学、メディア論などの知見を統合している点は本書独自の強み。
- 「解毒剤」概念の提示:陰謀論を単なる批判対象とせず、社会的対応策を正面から論じている。
- 日本事例の豊富さ:コロナ禍や選挙に関連する陰謀論が具体的に分析されており、読者自身の生活との距離感が近い。
こんな読者におすすめ
- 陰謀論やフェイクニュースが社会分断をどう深めるかを学びたい人。
- 日本の事例を通じて実践的な対策や教育的視点を得たい人。
- 学術的知見をベースにしながらも、社会的課題解決を模索する研究者や実務家。
デマ・陰謀論・カルト
著者:物江 潤|発売年月:2022年11月17日
概要(どんな本?)
本書は、社会に蔓延する「デマ」「陰謀論」「カルト」を総合的に扱い、その背後にある人間心理や社会構造を解説した一冊です。著者は長年にわたり宗教や社会運動を研究してきた社会学者であり、カルトの勧誘手口からネット上のフェイク情報まで、幅広い現象を実証的に分析しています。特徴的なのは、陰謀論を「異常な信念」として片付けるのではなく、誰もが陥りうる思考の落とし穴として位置づけ、その共通点と連続性を明らかにしている点です。
本書のねらいと構成(要点)
- デマの社会的機能:不安や危機の中でデマが拡散する仕組みを歴史的事例から考察。
- 陰謀論の心理学:偶然や不確実性を「誰かの意図」として理解したがる傾向を整理。
- カルトの構造:カリスマ的指導者と閉鎖的コミュニティが形成される過程を分析。
- デマ・陰謀論・カルトの連続性:三者を別物ではなく、同じ土壌から生まれる現象として描く。
- 現代社会への警鐘:SNSによる拡散のスピードが、従来以上に社会的リスクを高めていることを指摘。
主な口コミ・評判(深掘り)
肯定的評価
- 「デマ・陰謀論・カルトを一体的に扱った点が新鮮で分かりやすい」と高評価。
- 読みやすく、専門知識がなくても理解できると初心者にも支持されている。
- 「現代日本での事例が多く、身近に感じられる」という声が多い。
中間評価
- 幅広いテーマを扱っているため、「一つひとつの掘り下げは浅い」と感じる読者もいる。
- 学術書というより一般向け啓蒙書としての性格が強く、「研究的な裏付けをもっと知りたい」というニーズにはやや不足。
批判的評価
- 「実際のカルト被害者の証言や具体的な対策にもう少し踏み込んで欲しかった」との意見。
- 陰謀論に関する最新の海外事例が少ない点を物足りないとする声もある。
専門的に見た読みどころ
- 「三位一体」での理解:デマ・陰謀論・カルトを相互に関連づけることで、社会的リスクを俯瞰できる。
- 社会心理学的アプローチ:不安や孤立が人をいかにして信念へ導くかを明快に解説。
- 日本社会に即した事例:国内の事件や報道を多く参照しており、読者にとって距離感が近い。
こんな読者におすすめ
- デマや陰謀論、カルトを包括的に理解したい入門者。
- 社会学や心理学をベースに現代社会の課題を学びたい人。
- 教育・報道・行政などで、情報リテラシー啓発に携わる実務家。
陰謀論入門: 誰が、なぜ信じるのか?
著者:ジョゼフ・E・ユージンスキ|翻訳:北村京子|発売年月:2022年4月28日
概要(どんな本?)
本書は、アメリカを代表する陰謀論研究者ジョゼフ・E・ユージンスキが一般読者向けにまとめた「陰謀論の基礎解説書」です。著者はフロリダ大学の政治学者で、長年にわたり世論調査や統計分析を通じて、陰謀論がどのように人々の意識に浸透するのかを研究してきました。本書では、陰謀論の定義や歴史的背景、信じやすい人々の特徴、拡散の仕組みを分かりやすく紹介しています。タイトルにある通り「誰が、なぜ信じるのか?」という問いに答えることが中心テーマです。
本書のねらいと構成(要点)
- 陰謀論の定義:どんな説を「陰謀論」と呼ぶのか、学術的に整理。
- 歴史的視点:冷戦期から現代まで、アメリカ社会を揺さぶってきた代表的陰謀論を紹介。
- 心理的要因:人が陰謀論に惹かれる理由を、認知バイアスや不安感から解説。
- 社会的要因:格差や政治的不信が陰謀論を助長する土壌になることを指摘。
- 陰謀論の拡散:メディア、特にインターネットとSNSがどのように増幅しているかを分析。
主な口コミ・評判(深掘り)
肯定的評価
- 「学術的な知見を分かりやすく整理した入門書」として高い評価。
- 初めて陰謀論を学ぶ人にとって、全体像を理解できる良書との声が多い。
- 著者が長年にわたってデータを集めてきたため、理論だけでなく実証的な裏付けがある点が好評。
中間評価
- アメリカ事例に比重が大きく、日本社会に直結させるには補足が必要と感じる読者もいる。
- 入門向けであるがゆえに、深掘りした分析を期待した研究者には物足りない印象。
批判的評価
- 「具体的な対策や解決策の提示は少ない」との不満。
- 翻訳書としては読みやすいが、学術用語の多さが読みにくさにつながるという意見もある。
専門的に見た読みどころ
- 「誰が信じるのか」を実証的に検証:世論調査データを用いた分析は他書にない強み。
- 歴史と現代をつなぐ:古典的陰謀論からSNS時代の事例までを連続的に理解できる。
- 政治学の視点:陰謀論を「民主主義の機能」との関係で捉える視点は、他の心理学中心の書籍と一線を画す。
こんな読者におすすめ
- 陰謀論の基礎を体系的に学びたい入門者。
- 社会心理学や政治学の観点からデータに基づいた説明を求める人。
- フェイクニュースや情報リテラシー教育の教材を探している教育関係者。
SNS時代の戦略兵器 陰謀論 民主主義をむしばむ認知戦の脅威
著者:長迫 智子、小谷 賢、大澤 淳|発売年月:2025年1月24日
概要(どんな本?)
本書は、陰謀論を「個人の誤信」ではなく、国家や組織が戦略的に利用する認知戦(Cognitive Warfare)の武器として捉えた研究書です。SNSの普及によって、陰謀論はかつてないスピードと規模で拡散し、社会分断や民主主義の弱体化を引き起こしています。本書は、国際政治学・安全保障研究・メディア研究の専門家が共同執筆し、陰謀論がいかにして「戦略兵器」と化すのかを分析。ロシアや中国による情報操作の事例から、米国・日本における陰謀論の拡散まで、地政学的文脈も交えて解説しています。
本書のねらいと構成(要点)
- 陰謀論の軍事利用:国家が敵国や自国民に対して陰謀論を操作し、信頼を揺るがす手口を紹介。
- SNSの加速装置:アルゴリズムと拡散構造が、偽情報の爆発的な広がりを可能にしている点を分析。
- 国際事例:ロシアのプロパガンダ、中国の情報戦、米国のQアノンなどをケーススタディ化。
- 日本への影響:国内政治や社会運動における陰謀論の広がりと、そのリスクを提示。
- 対抗策:情報リテラシー教育や制度的規制、国家レベルの戦略対応の必要性を論じる。
主な口コミ・評判(深掘り)
肯定的評価
- 「陰謀論を国家安全保障の文脈で語る視点は新しい」と高評価。
- 「国際事例が豊富で、地政学と結びつけて理解できる」点が専門家や学生に支持されている。
- 一般向けながらも内容が本格的で、政策研究の入門としても使えるという意見がある。
中間評価
- 扱うテーマが広いため、「各国事例の説明が駆け足に感じる」という声。
- 分析は鋭いが、具体的な防御策や実務的な応用に物足りなさを感じる読者もいる。
批判的評価
- 学術的な記述が多く、一般読者にはやや難解との指摘。
- 「陰謀論を戦略兵器と断定する論調が強く、柔軟な視点に欠ける」との批判も見られる。
専門的に見た読みどころ
- 認知戦の視点:従来の「個人心理」中心の陰謀論研究に対し、地政学・安全保障の次元で論じている点が独自。
- SNSの構造的役割:単なる道具ではなく、国家戦略の一部としてSNSが機能するという問題提起。
- 実務的意義:安全保障・政策・教育の現場における警鐘として活用できる。
こんな読者におすすめ
- 陰謀論を国際安全保障や地政学の観点から理解したい人。
- 政策立案やリスク管理に関わる実務家。
- SNS時代の情報戦に関心を持つ研究者や学生。
日本人が知らない「陰謀論」の裏側 米国大統領選挙で変わる日本と世界の運命
著者:やまたつ|発売年月:2024年3月27日
概要(どんな本?)
本書は、アメリカ大統領選挙を舞台に広がった数々の陰謀論を切り口に、現代政治と国際社会の裏側を解説した一冊です。著者やまたつは、国際政治・安全保障をテーマに執筆活動を続けてきた評論家であり、日本のメディアでは十分に報じられない情報や、欧米で拡散した陰謀論の実態を分かりやすく紹介しています。トランプ前大統領をめぐる選挙不正説、Qアノンの動き、さらには米国発の陰謀論が日本社会や国際秩序にどう影響するのかを具体的に描き出します。タイトル通り「日本人が知らない」視点を前面に出し、海外情報と国内への波及をつなぐ構成になっています。
本書のねらいと構成(要点)
- 米大統領選挙と陰謀論:不正選挙説や議会襲撃事件を事例に、陰謀論が政治を揺さぶる過程を描写。
- Qアノンの影響力:ネット掲示板からSNSへ拡散した陰謀論の力を整理。
- 日本への波及:米国の陰謀論が日本のネット空間や一部の政治運動にどう輸入されているかを紹介。
- 世界秩序との関連:米国の政治不安が同盟国や国際関係に与えるリスクを分析。
- 著者独自の視点:日本メディアでは取り上げられにくい海外情報を掘り下げて提示。
主な口コミ・評判(深掘り)
肯定的評価
- 「米国の陰謀論と国際政治を結びつけて解説している点がわかりやすい」と評価。
- 日本語でまとまったQアノンや選挙不正説の解説書は少なく、情報源として貴重との声が多い。
- 著者の切り口が明快で、一般読者にも理解しやすいと好評。
中間評価
- 「国際政治の視点は興味深いが、分析よりも紹介に比重がある」との感想。
- 海外報道をベースにしているため、「一次資料の裏付けが弱い」と感じる読者もいる。
批判的評価
- 著者の立場や論調に強さがあり、「やや陰謀論的な見方に寄りすぎているのでは」と懸念する声もある。
- 学術的な研究書というより、ジャーナリスティックな解説に近いとする批判。
専門的に見た読みどころ
- 米国政治と陰謀論の接合点:不正選挙説が民主主義を脅かすプロセスを、日本人読者にも理解できる形で提示。
- 国際的視点:陰謀論を一国の問題ではなく、国際秩序の不安定化と結びつけて論じている。
- 情報輸入の仕組み:米国の陰謀論がどのように日本の一部に伝播しているかを知る貴重な資料。
こんな読者におすすめ
- 米大統領選挙やQアノンをテーマにした陰謀論を詳しく知りたい人。
- 国際政治と情報空間の関係に関心を持つ社会人や学生。
- 日本のメディアだけでは得られない海外の視点を取り入れたい読者。
陰謀論関連書籍まとめ表
| 番号 | タイトル | 著者 | 発売年月 | 主な特徴 | 評判の傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | となりの陰謀論 | 烏谷昌幸 | 2025年6月 | 陰謀論を「隣の問題」として捉え直し、パラレルワールド概念で解説 | 読みやすく入門に最適と高評価、ただし米国事例中心との指摘も |
| 2 | 陰謀論はなぜ生まれるのか Qアノンとソーシャルメディア | マイク・ロスチャイルド(翻訳:烏谷昌幸・昇亜美子) | 2023年 | Qアノンの発生から拡散、政治への影響をルポ的に描写 | Qアノン理解の決定版と評価、日本事例が少ないとの声 |
| 3 | 陰謀論-民主主義を揺るがすメカニズム | 秦 正樹 | 2022年10月20日 | 陰謀論の心理・社会・政治メカニズムを学術的に整理 | 学術的で体系的と高評価、一般読者にはやや難解との意見 |
| 4 | 社会分断と陰謀論 虚偽情報があふれる時代の解毒剤 | 雨宮 純、烏谷 昌幸、長迫 智子、上野 庸平、岡部 友樹 | 2025年5月15日 | 分断と陰謀論の関係を多角的に分析、「解毒剤」を提案 | 多角的で実践的と好評、掘り下げ不足を指摘する声も |
| 5 | デマ・陰謀論・カルト | 物江 潤 | 2022年11月17日 | デマ・陰謀論・カルトを一体的に扱い、その連続性を解説 | 分かりやすいと初心者に好評、深掘り不足との評価も |
| 6 | 陰謀論入門: 誰が、なぜ信じるのか? | ジョゼフ・E・ユージンスキ(翻訳:北村京子) | 2022年4月28日 | 誰が陰謀論を信じるのかをデータで分析、政治学的視点 | 入門に最適と高評価、解決策が少ない点に不満も |
| 7 | SNS時代の戦略兵器 陰謀論 民主主義をむしばむ認知戦の脅威 | 長迫 智子、小谷 賢、大澤 淳 | 2025年1月24日 | 陰謀論を「認知戦の武器」と捉え、国際事例を交えて分析 | 安全保障視点が新しいと好評、難解で断定的との批判も |
| 8 | 日本人が知らない「陰謀論」の裏側 米国大統領選挙で変わる日本と世界の運命 | やまたつ | 2024年3月27日 | 米大統領選と陰謀論を軸に、日本への影響を解説 | 日本語で得られる米国陰謀論解説として貴重、やや論調が強いとの声 |
まとめ
今回紹介した8冊は、それぞれ視点や対象が異なります。
- 入門書として学びたい人には「となりの陰謀論」「陰謀論入門」。
- Qアノンを詳しく知りたい人には「陰謀論はなぜ生まれるのか」。
- 学術的・体系的に理解したい人には「陰謀論-民主主義を揺るがすメカニズム」。
- 日本社会の文脈や実践的対策を重視するなら「社会分断と陰謀論」「デマ・陰謀論・カルト」。
- 国際安全保障や情報戦の視点を求めるなら「SNS時代の戦略兵器 陰謀論」。
- 米国政治と日本への影響を読み解きたいなら「日本人が知らない『陰謀論』の裏側」。
読者の関心に合わせて読むべき一冊が変わるラインナップになっており、陰謀論というテーマを「個人心理」から「国際政治」まで多面的に学ぶことができます。