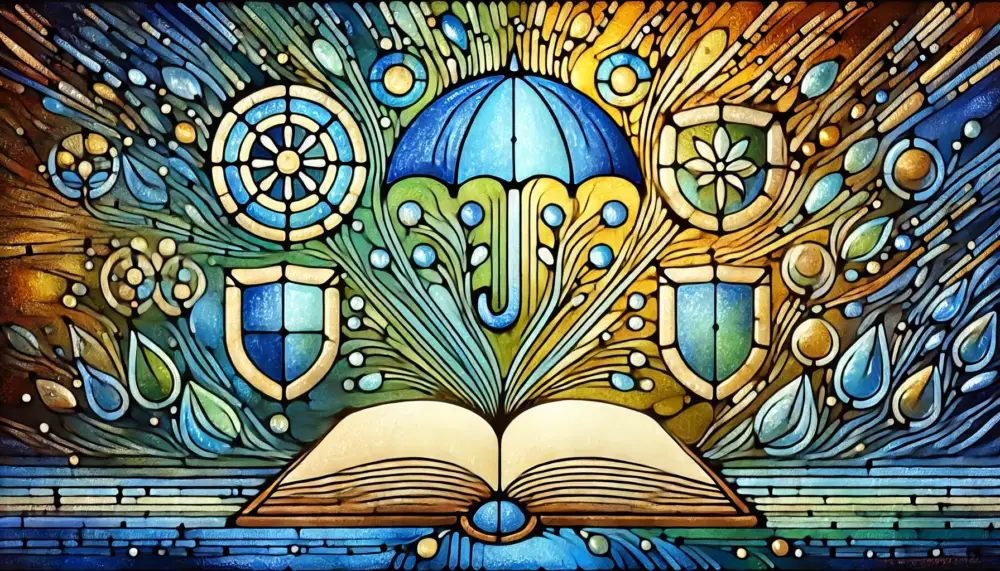日々の生活や将来設計において、「保険」はとても身近だけれど、同時に分かりにくいテーマでもあります。商品が多様で条件が複雑、制度が変わることもあり、どこを見て選べばいいか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
そこで、保険を「知る」「選ぶ」「見直す」の3つのフェーズに分けて、それぞれに役立つ本を5冊ピックアップしました。それぞれ著者の立場、対象とする読者、内容の深さや特徴が異なります。本記事では、各本の要点・評判を整理しながら、「あなたにとって今、どの本を読むのが最も有用か」が見えてくるよう比較していきます。
保険ビジネス 契約者から専門家まで楽しく読める保険の教養
著者:植村 信保/発売年月:2025年8月

本の概要
この本は、「保険とは何か」を生活者・契約者の立場から基本的な疑問を投げかけ、それを業界構造や制度、リスク管理、未来技術といった専門的なテーマへつなげていく構成になっています。著者は、損害保険会社勤務、格付け会社アナリスト、金融庁の任期付職員など、保険業界を多角的に経験している人物で、現在は大学教員として教える傍ら、保険の経営・制度・リスクの観点から論じています。内容は平明ながら、制度や動向、将来展望まで含まれており、ビジネス教養としても、業界内部を知る入門としても価値が高いです。
章立てとしては、たとえば「そもそも保険には入っておいたほうがいいのか」「生命保険と損害保険との違い」「保険と貯蓄の考え方」など、既存の常識を問い直すテーマから始まり、最後には「最新テクノロジーから学ぶ未来の保険の世界」として、自動運転などの技術が保険をどう変えるかという未来思考的な話に至ります。
主な口コミ・評判
肯定的な意見
- 読みやすさを評価する声が多く、「保険に詳しくなくても取っつきやすい」という点が支持されています。
- 未来章、特にテクノロジー関連の展開(自動運転など)が興味深いという意見が目立ちます。
- 保険の“素朴な疑問”にきちんと答えてくれているため、「自分で判断するための軸」が見えるという感想があります。
中立的な意見
- 内容は広く浅く論点を網羅しているが、どこかで深掘りが足りない、という指摘もあります。
- 図表が少なく、文章中心なので“イメージ”で理解したい人には工夫が必要、という声。
- 業界外の人には十分な教養になるが、業界内の専門家には物足りない部分がある、という感想。
批判的な意見・留意点
- 数理や制度の細部、改正条文レベルなどを期待していた場合、それらはあまり深く扱われていない。
- 図や表が少ないため、視覚的に整理された情報を求める読者には読みづらいと感じる部分がある。
- 専門的な政策動向や規制・会計基準などの最新アップデートを追うには、補助資料が必要という声。
深掘りポイントと「なぜおすすめか」
- 判断軸を持たせる設計
この本で特に重要なのは、「保険を選択するとき/何を考慮すべきか」という判断軸を提示していることです。単に商品を比較するだけでなく「自分の生活状況・抱えているリスクは何か」「そのリスクが実際どの程度コストをもたらすか」「公的制度・民間保険の役割分担はどうあるべきか」というレベルで思考させてくれます。このため、「保険不要論」や売り手側の宣伝に惑わされない力をつけたい読者には非常に有効です。 - 制度・業界構造への入り口としての幅広さ
保険というテーマは、生命保険/損害保険、保険会社の収益構造、販売チャネル、法規制、会計基準、リスク管理など多岐にわたります。本書はそれらを「素朴な問い→本質的要素→未来変化」という流れで整理しており、初めて保険を真剣に考える人にとって、どのテーマをさらに学べばよいかの“ガイド”になります。 - 未来技術への考察
自動運転、データ利用・AI・ウェアラブルなど、保険を取り巻くテクノロジーがどう制度や商品に影響するかが論じられており、将来を見据える学びがある点も強みです。現時点では実用化が進んでいないテーマだとしても、その“可能性とリスク”を整理しておくことは、契約者・業界関係者双方にとって価値があります。
NEWよい保険・悪い保険2025年版
著者:横川由理、長尾義弘/発売年月:2024年11月

本の概要
このムックは、保険の“コストパフォーマンス”を重視し、消費者目線で「よい保険」「悪い保険」を実名で比較・評価することを目的としています。16の保険分野(医療保険・がん保険・生命保険・火災保険など)が対象で、それぞれの保障内容をプロが厳しくチェックし、ランキング形式でベストおよびワースト商品を選出しています。
さらに、家計リスク別・年代別・状況別でどんな保険の組み合わせが合理的かを提案していたり、保険を見直す際のコツや注意点、最近の経済・制度変化(新NISA、インフレ、円安など)が保険選びに与える影響にも言及しており、初心者でもリアルタイムの“新常識”を把握できるようになっています。広告や忖度が排されており、純粋に消費者ファーストの情報提供が意図されています。
主な口コミ・評判の傾向
肯定的な意見
- 「種類ごとに保険の良し悪しがわかりやすく紹介されている」「点数評価が明確なので比較検討しやすい」といった感想が目立ちます。
- 新しい制度変化やマーケットトレンド(インフレ・円安など)を反映しており、いま現在の保険選びに役立つ内容だ、という声。
- “広告なし”“忖度なし”という宣言が信用できる、という安心感を感じる読者が多い。
中立的な意見
- 概観として役立つが、それぞれの保険商品の細かい内部条件(免責条項・給付率・解約返戻金など)の比較や将来の制度変更のリスクまで含めた比較が十分というわけではない、という指摘。
- この種のランキングものは「一発でベスト」が見つかるが、自分の生活状況・リスクプロファイルに応じた微調整が必要という見方。
批判的な意見・留意点
- 評価が「現在時点での保障内容・コスパ重視」であるため、将来何らかの制度変更や商品の改定があった場合にはすぐに古くなる可能性がある、という懸念。
- 「ワースト保険」の評価が過度に怖さを煽るように感じるという読者もおり、情報受け手が過度に不安になる可能性があるという意見。
- 保険商品の多様性が増えてきており、ランキング対象外の商品や、地域・販売チャネルによって入手条件・価格が異なる商品では比較が難しいという声。
深掘り解説:何が“比較・選択”に効くか
- ランキング仕様の利点と限界
項目別ランキング(16分野)という形式は、まず“どの保険が他と比べて優れているか・劣っているか”を一目で知るには非常に便利です。とくに初めて保険を比較する人にとって、自分の関心分野(たとえば医療/がん/生命など)で「上位の保障内容とは何か」が見えるのは大きい。ただし、そのランキングの基準(保険期間、医療技術の進展、地理的条件など)が読者自身の状況と合致するかを確認する必要があります。 - 最近の制度・経済動向の反映
新NISAや円安・インフレなど、保険以外のお金に関する変化が保険契約や保険料・給付実質にどう影響するかを説明している点が現状重視派には高評価です。保険を単体で見るのではなく、家計・資産運用・税制などとの関係で保険の役割を再定義できる材料となっています。 - “見直し”というテーマ
年齢・状況別にベストな保険の組み合わせを提案していたり、見直す際の“落とし穴”を指摘しているため、すでに加入している保険をどう見直すか考えている読者には特に実用的です。比較的新しいしくみや保険料の支払い方法の選択肢なども含まれており、「いま契約すべきか待つべきか」「どの保障を削るか・追加するか」の判断材料になります。
なぜテーマ理解の入門・実用書として薦められるのか
- 保険を“買う前”だけでなく、“見直す/捨てる・変更する”場面にも応用できる設計になっている。
- 多数の保険商品の実名比較という点で、読者が口コミや広告情報に振り回されずに自分で判断軸を持てるよう支援している。
- ランキング+コツ+最近の制度変化という三本柱が揃っており、「現状把握 → 比較 → 自分なりの判断」というプロセスをこの一冊で経験できる。
1日1分読むだけで身につく保険の選び方大全100
著者:長尾 義弘/発売年月:2024年10月
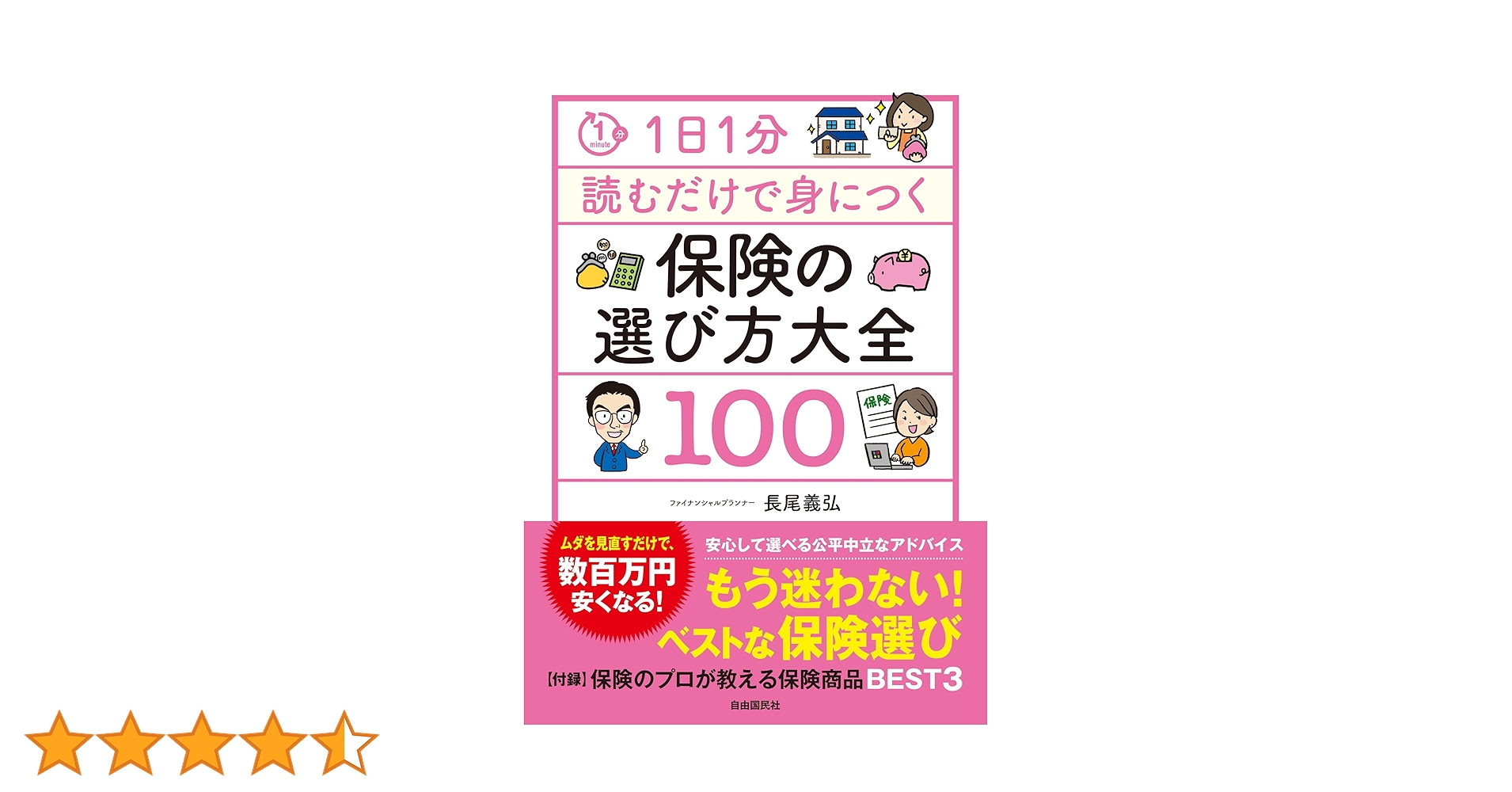
本の概要
この本は、忙しい人でも「毎日1分読むだけ」で保険についての理解を深め、自分に合った保険を選べるようになることを目的としています。シリーズ形式で、見開き一題材+イラストや図版で構成されており、保険の基本から見直しのポイント、損害保険の入り方まで、100の選び方・考えるべきポイントを網羅しています。
ジャンルとしては、生命保険(終身・定期・収入保障など)、医療・がん保険、火災・就業不能・介護・認知症保険など損害領域も扱い、加入前・見直し時・将来を見据えた判断基準を提示することで、「なんとなく入る」「薦められるままに入る」という選択をしない読者を育てることを意図しています。
主な口コミ・評判の傾向
肯定的な意見
- 図やイラストを用いて説明がわかりやすい、という声。専門用語・仕組みなどがビジュアルで把握できるので、理解しやすいとのこと。
- 見直しを考えていた契約者が、「自分にとってどんな保障が不要か・どこを削るか」が明確になったと感じている例が多い。
- 選択肢の比較に“辛口コメント”が付いており、メリットだけでなくデメリットも含めて公平に見せてくれる点が高評価されている。
中立的な意見
- 全体として良質だが、「もっと専門的な深掘りを期待していた」という意見もあり。特に数理計算・将来制度変更・保険会社ごとの詳細比較などは本書では簡易な扱い。
- 内容は幅広いため、自分の関心分野に応じて使う部分と飛ばす部分が出てくる。構成上、断片的に読むスタイルを好む人には向いている、一方で連続して深く学びたい人には物足りないとの意見。
批判的な意見・留意点
- 保険の比較にあたって、「販売チャネルの違い」や「地域・年齢・健康状態の個別性」の影響を十分に踏まえていないケースがあり、「この保険はいい」「この特約は不要」と断定する言い方に過度の一般化を感じる、という批判。
- 見開きでの説明という形式ゆえに、「1つのテーマを1日1分で掘り下げる」のには限界があり、たとえば免責・特約など細かい契約条件の差異をきちんと読みこむ力を養うためには別資料が必要。
- 保険商品の最新改定/制度変更(税制、医療制度、保険会社の引受基準など)への追随が本書執筆時点まで、ということもあり、将来の変化が反映されていない部分があるとの指摘。
深掘りポイントと「おすすめ理由」
- 短時間で“判断基準”を手に入れるスタイル
本書の最大の特徴は「1日1分」というペースで読めること。まとまった時間が取れない人でも毎日続けやすく、保険を選ぶ際の観点を積み重ねていける設計です。これによって、保険広告のキャッチコピーやセールスの言葉に振り回されず、自分の尺度で“何を見るべきか”を養えます。 - 公平中立な立場からの解説
著者は“保険を売ったことがない”という立場を明示しており、「加入者側」の視点が中心です。これにより、保障内容の過去・現在・将来を比較する際に、販売側の都合や収益構造に左右されない比較・判断の材料が得られます。例えば、終身保険の使いどころ・使いにくさ、医療保険と公的医療制度との重複、特約の意味とコストのバランスなど。 - 構成のバランス:基礎から見直し・損害保険まで
保険初心者がまず知るべきこと(保険は本当に必要か、自分に合った保障とは何か)から始まり、その後生命保険のしくみ、見直す時のポイント、そして損害保険の“得な入り方”と範囲を広げていく構成。これにより、「新しく入るべきか」「既存契約をどう扱うか」「どんな保険を追加するか」の3つの場面で使える知識が揃っています。 - 実用性と注意点の両立
単に“こういう保険が良い/悪い”だけでなく、注意すべき契約条件(免責・給付率・期間・特約・更新型 vs 終身型など)やコストの無駄を減らす方法を提示しているので、加入だけでなく“損しない契約設計”へのヒントが多く含まれています。
書けばわかる! わが家にピッタリな保険の選び方 第2版
著者:末永 健/発売年月:2020年5月
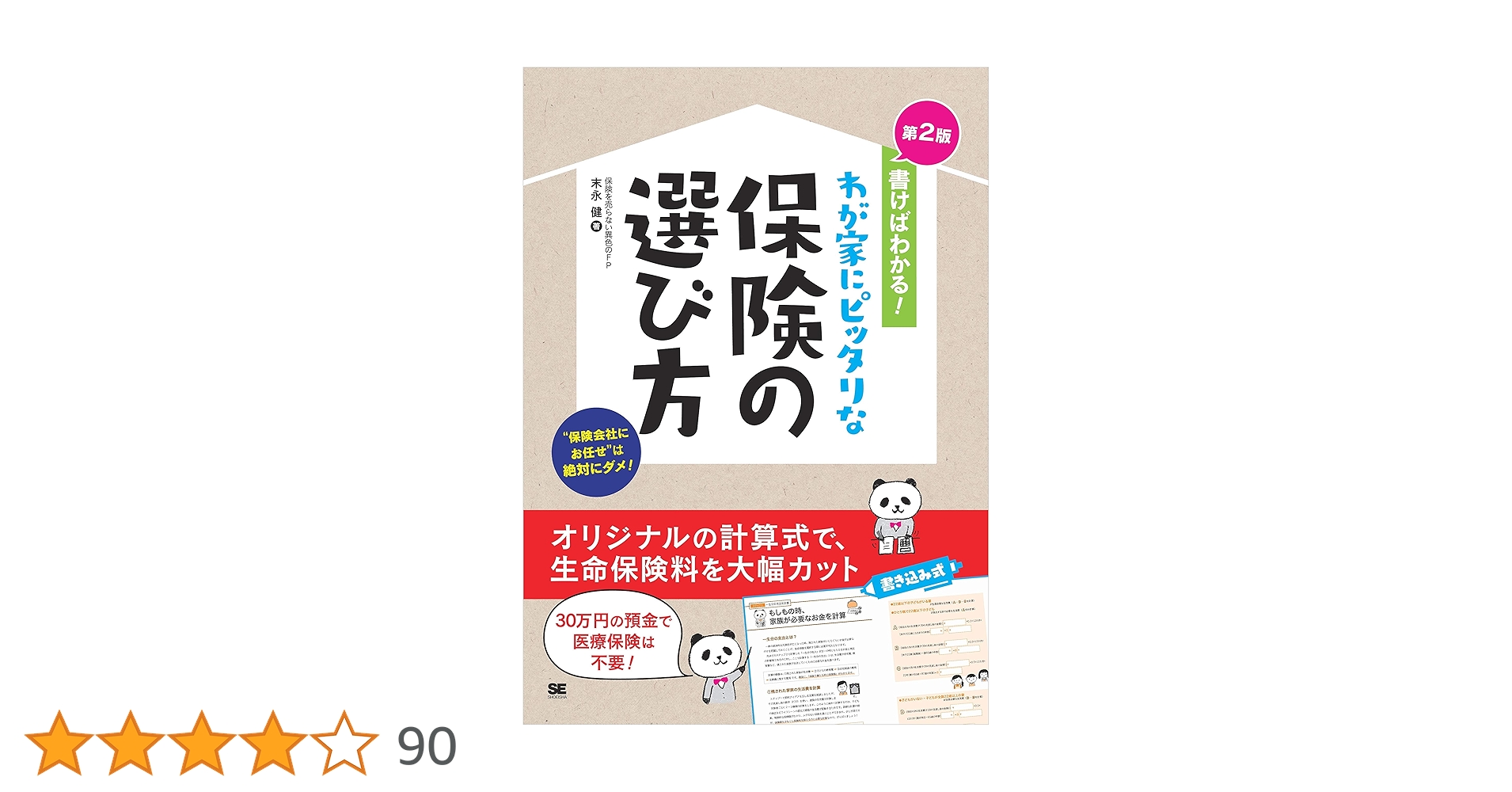
本の概要
この本は、「家族構成・経済状況・ライフプランなど“わが家”の条件」にあわせて、どの程度の保障が必要かを自分で計算し、適切な保険を選ぶ力を養うことを目的としています。「オリジナル計算式」を使って、保障額を具体的に算出するワーク形式のページがあり、読み手が“自分で考えて判断する”ことを重視しています。
構成は以下のような流れになっています:
- 保険の基本的なしくみや種類の整理
- わが家に必要な保障額を具体的に算出する章
- 生命保険の中で「入るべき/入るべきでない」ものを見分ける基準
- 医療保険が本当に必要かを問い直し、公的制度・貯蓄とのバランスを考える章
- 見直しのポイント、保険会社や販売チャネルに関して注意すべきことの解説
全体として、「保障が多ければ安心」という漠然とした考えを持つ人に、コストを無駄にしない選び方を教えてくれる内容です。
主な口コミ・評判の傾向
肯定的な意見
- 自分で保障額を数字で出せるようになる部分が好評。計算式を使って、「今何が必要か/何を削れるか」が見えてきた、という声が多い。
- 保険よりも貯蓄・節約・公的制度の活用など、「保険以外の選択肢」をちゃんと提示していることが、読者に安心感を与えているという意見。
- 見直しの“きっかけ”として良い本との評価。「なんとなく入っていた保険」が自分の生活に合っていないことに気づけたという人が多い。
中立的な意見
- 保険の種類や制度の全体像を理解するには十分だが、細かい商品設計/引受基準/保険会社による差異などの“実務的細部”については浅いと感じる人もいる。
- ワーク形式や書き込み式の計算が役立つが、家計や将来設計が変わったときに再度見直す必要がある、“使い捨てにならないように使い続ける教材”としての工夫が必要、という意見。
批判的な意見・留意点
- 医療保険不要論を強めに打ち出している部分があり、その主張に懸念を示す人も。「もしものときに備える」という立場からは、公的制度だけではカバーしきれない事例もあるため、完全に不要という判断には慎重であるべきという声。
- 計算式で出した保障額が実際の保険商品の提供範囲や価格・条件と食い違うことがあり、商品を比較する際には追加で調べる手間が出る、という指摘。
- 発行から時間が経っているため、制度変更・保険商品の改定などの最新情報が反映されていない可能性がある、という注意。
深掘りポイントと「おすすめ理由」
- “オリジナル計算式”を通じて判断力を養う
本書の大きな強みは、ただ「こういう保障が望ましい」という理想論を述べるだけでなく、自分の収入・支出・生活スタイルに応じて具体的な金額を出すワークがあるところです。これによって、保険会社や代理店が提示する数字を鵜呑みにせず、自分なりの基準で「十分/過剰/不足」を判断できるようになります。 - 公的制度・貯蓄・節約との比較軸を持たせる点
保険を“唯一の備え”と考えるのではなく、公的医療制度・社会保障・家族の貯蓄などと重ねながら保険の役割を位置づける視点が、本書を実用的なものにしている理由です。無駄な保険料を払うより、まず生活費の見直しや不必要な支出を削ることが可能な部分を示してくれる点が“家計防衛”観点でも価値があります。 - 見直し促進のきっかけとして機能する
本書は「保険を見直してみよう」というアクションにつながる構成になっています。「この保証はいらないかもしれない」「こんな特約は見直せる可能性がある」という具体的な手がかりが豊富で、読者が行動に移しやすい設計です。実際、読者レビューでも「ムダに入っていた保険を減らせた」「保険料が節約できて家計が楽になった」といった声が見られます。 - 注意点:情報の“鮮度”と個別性
本書の内容は発行年の現場・制度に基づくものなので、制度の改正・税制の変化・保険会社の商品の更新などには注意が必要です。また、保障が必要な状況(家族構成・健康状態・地域・将来のライフプラン)が人によって大きく異なるため、「本書の計算式 → 出た数字」がそのままあてはまるとは限りません。補助的に最新の商品パンフレット、FP・保険相談などの情報も活用するのが望ましいです。
保険選びはこの1冊で大丈夫 いまさら聞けない 保険の超基本
著者:保険営業専門学校/発売年月:2025年2月
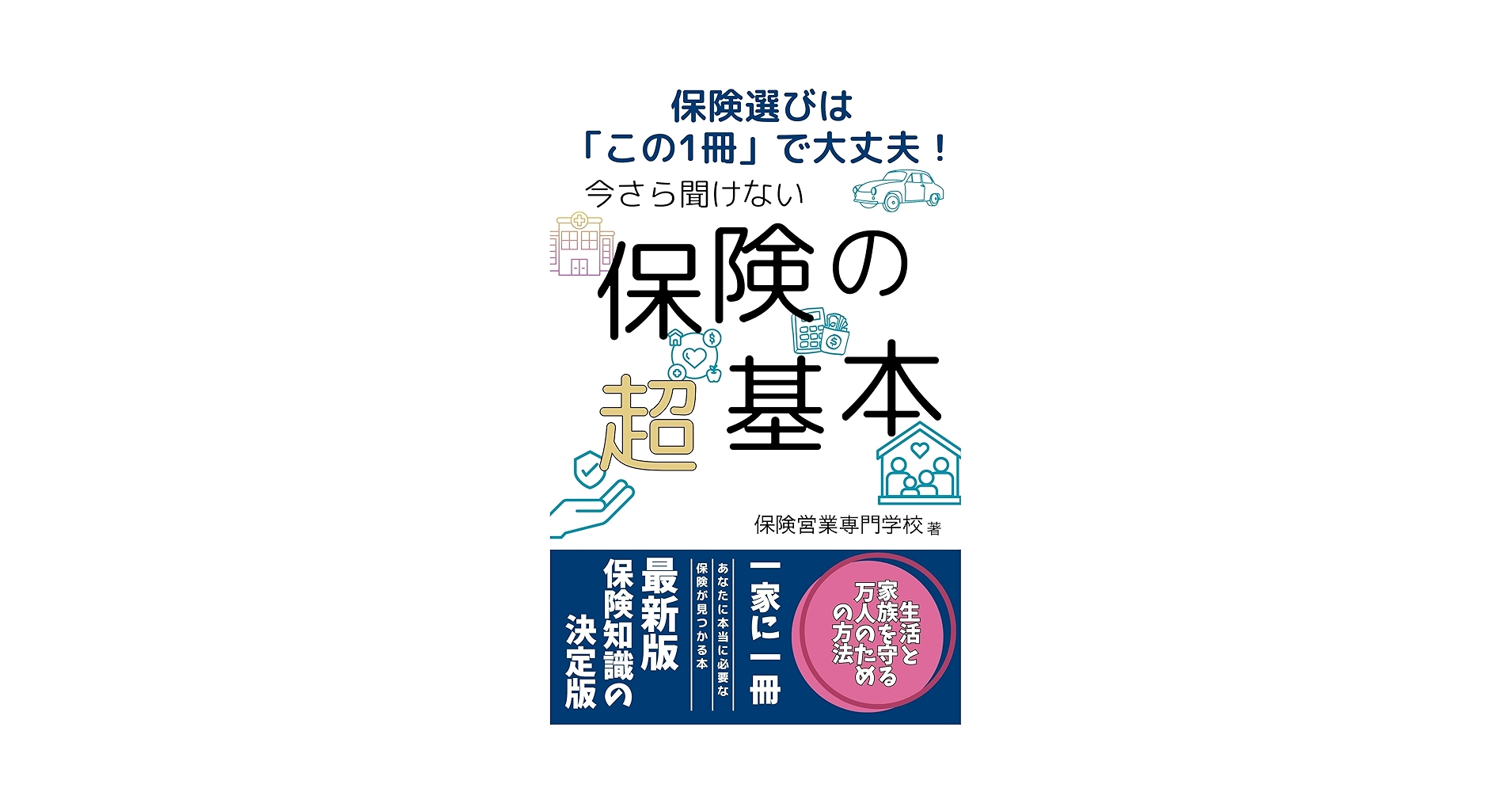
本の概要
この本は、保険というものをまったく知らない人や、これまで「保険について聞きたいけれど聞けなかった」人を対象に、保険の基本的な考え方・仕組みを一から丁寧に解説することを目的としています。名前のとおり「いまさら聞けない」レベルの疑問──例えば、生命保険と損害保険の違い、保険料がどう決まるか、加入・見直しの際の注意点など──を取り上げ、それぞれについて専門用語をかみ砕いて説明しています。
章構成は、まず保険の「なぜ」に始まり、「種類」「保障内容」「特約」「販売方法」「契約者の権利・義務」「見直すタイミング」「保険会社の倒産・契約トラブル」など、現実に契約前・契約後で疑問になるポイントをカバーしています。また、読者が“基礎用語”で混乱しがちな言葉(免責・満期返戻金・更新型 vs 終身型など)を整理するコラムもあり、入門者が誤解しやすい論点をクリアにする工夫があります。
主な口コミ・評判の傾向
肯定的な意見
- 保険初心者にとって「これまで曖昧だったこと」が明確になる、というコメントが多く、入門書としては満足度が高いという声があります。
- わかりやすい言葉と具体例が多く、営業用語や業界用語に疎い人でも読み進めやすい点が評価されています。
- 契約トラブルや特約の落とし穴など、「知らないと損すること」が実例を交えて紹介されているので、読後に「自分の保険をチェックしてみよう」という気になるという感想があります。
中立的な意見
- 基本を押さえてはいるものの、「深さ」は限られており、具体的な保険商品の比較や数理的裏付けなどを求める読者には物足りない、という意見もあります。
- 入門書としての目的は果たしているが、最新制度や税制・医療制度の改正まで取り込んでいるわけではないため、そこは補足が要る、という指摘があります。
批判的な意見・留意点
- 保障内容や保険料の決まり方など、一般論の説明が中心で、地域・年齢・健康状態など個別ケースの差異が乏しいという声があり、自分の場合にどこまであてはまるか不明な点がある、といった評価があります。
- 短めの章・説明が多いため、「もっと突っ込んだ内容」がほしい人には物足りなさを感じることがあるようです。
- 営業学校が著者ということもあり、「販売者視点が多少混じっているのでは?」という疑念を持つ人もいて、完全に中立とは言い切れないとの見方もあります。
深掘りポイントと「おすすめ理由」
- 初心者が最初に抑えるべき“核”を網羅している
この本の強みは、保険を一歩も知らない状態からでも、「保険とは何か」「どう使うか」「何を見て契約すればいいか」といった、基礎的な判断軸を体系的に教えてくれることです。保障内容・特約・販売形態・契約者の立場での注意点などを欠かさず含めており、基礎固めに非常に適しています。 - 誤解しやすい用語と制度の整理
“更新型 vs 終身型”や「特約」「免責条項」「満期返戻金」「給付条件」など、実務で混乱しがちな用語を入門者向けにやさしく整理してくれているので、本やパンフレットを読む際の理解が進みます。これにより、保険会社の説明やパンフの数字を“見せかけ”だけで判断しない態度が身につきます。 - 契約後の場面・トラブル注意点や見直しのタイミング提示
契約後に起こる可能性のある“契約トラブル”(保険会社との認識差異、免責等)や、“必要保障の変化”(結婚・出産・転職・老後などで保障が過剰/不足になること)など、読者が契約した後も定期的に見直すべきポイントを示している点が実用性を高めています。 - 注意すべき点
入門書であるため、具体的な保険商品の比較や保険料のシミュレーション、将来制度の変更への予測などは限定的です。契約者個人の健康状態・居住地・リスクプロフィール・年齢などによって保険の条件やコストが大きく変わるため、それらを本書だけで完全に把握することは難しいです。また、最新の制度変更・税制・医療技術の進展などが反映されていない可能性があるので、最新情報を別に確認することが望ましいです。
各本の特徴まとめ
| 書籍 | 対象レベル/読者像 | 主な内容の特徴 | 読みやすさ・構成スタイル |
|---|---|---|---|
| 保険ビジネス 契約者から専門家まで楽しく読める保険の教養 | 保険について「生活者としての疑問」から「業界・制度・将来技術」に興味がある人。初心者~中級者、また業界を知りたい人にも | 保険の本質・歴史・構造・業界の仕組み・中立性・テクノロジーの未来など広範にカバー。疑問→構造→未来という流れ。 | 各トピックが均一フォーマット。事例・コラムも使われているので読みやすく、部分読みもしやすい。 |
| NEW よい保険・悪い保険2025年版 | 保険商品を具体的に比較したい人。保障内容・コスパ重視、ランキングで選びたい人 | 保険商品を実名で「ベスト・ワースト」に評価。16分野にわたってチェック。さらに制度・経済動向を反映させた選び方・見直しのヒントあり。 | ランキング形式+ムック雑誌スタイルで、図表や比較表・評価が中心。視覚的にも入っていきやすい。 |
| 1日1分読むだけで身につく保険の選び方大全100 | 忙しい人、スキマ時間でちょっとずつ学びたい人。基本を広く押さえたい人 | 「保険必要性」「見直しポイント」「損害保険」「生命保険のしくみ」など100のチェックポイントで広く浅くカバー。著者が販売側ではなく加入者側視点を強調。 | 見開き式・イラスト・図版ありで軽快。1日1分というペースが設定されており、負担が小さい。 |
| 書けばわかる! わが家にピッタリな保険の選び方 第2版 | 家族・家計を重視する人、自分の生活に合った保障を具体的に設計したい人 | 家庭の状況を元に「保障額を計算する式」があり、見直し・節約・公的制度との比較が重視される。保障の過不足を数字で把握する実用性が高い。 | コンパクトかつワーク形式。計算式を使うページなど、手を動かしながら読める構成。入門+実践がバランス。 |
| 保険選びはこの1冊で大丈夫 いまさら聞けない 保険の超基本 | 保険の仕組み・用語・基礎から完全に初心者の人 | 保険の種類・特約・契約者の権利義務・見直しのタイミング・トラブルの回避など、「聞きたかった基礎」の整理が中心。 | 用語解説や具体例が多く、初心者に優しい。「売る側」ではなく「契約者/加入者」視点に立って書かれている印象。 |
比較:強み・限界・用途
| 比較軸 | 強みが大きい本 | 限界・注意点 |
|---|---|---|
| 理論・制度/業界構造の理解 | 「保険ビジネス」が最も深い。この本は保険業界の仕組み・歴史・規制・テクノロジーの未来など“構造”をきちんと解説しており、学術的・教養的な内容もある。 | 深掘り過ぎる内容を期待する人には足りない「数学・数理モデリング・具体的な最新制度改正の全て」などは別資料が必要。 |
| 商品比較・コスパ重視 | 「NEW よい保険・悪い保険2025年版」が明確で、実名ランキング+コスパ比較で“買っていいもの/避けたいもの”が見つけやすい。 | ランキングは“現時点”の保障内容・価格に依存するため、将来の商品改定やライフステージの変化に対応するためにはアップデートが必要。 |
| 速習・日常使いのヒント | 「1日1分読むだけで…」と「超基本」が非常に使いやすい。スキマ時間で知識を積みたい人や、基礎語彙・仕組みを整理したい人に向く。 | 浅めに広くという設計なので、専門的・非常に具体的な契約条件・引受基準などに踏み込んでいるわけではない。 |
| 自分で数字を使って設計する力 | 「書けばわかる!わが家にピッタリな保険の選び方」が最適。家計・生活条件に応じて、保障額を具体的に見積もるワークがある。 | ワーク形式なので、前提の数字(収入・支出・将来の変動など)次第で差が出る。実際の保険商品の価格や条件が自分の場合と異なることも多く、それを調べる補足が必要。 |
どの本を選ぶべきか:おすすめの人(使いどころ)
| 読者タイプ | 推奨本 | 補足的に読むとよい他の本 |
|---|---|---|
| 保険を全く知らない/これから契約を考えている初心者 | 「保険選びはこの1冊で大丈夫」「超基本」 | →その後「書けばわかる」「1日1分」で保証の見直し・比較感覚をつける |
| 自分にとって最良の保険を“今”選びたい/見直したい | 「書けばわかる!わが家にピッタリな保険の選び方」「NEW よい保険・悪い保険2025年版」 | →「保険ビジネス」で制度や業界の裏側を理解すると見直しの判断がより正確にできる |
| 保険業界・制度・将来を知りたい/仕事で関わる人 | 「保険ビジネス」 | →比較・実践重視の本(NEW よい保険・書けばわかるなど)を併読すると実務感がつかめる |
| 忙しいけど少しずつ知識を積みたい人 | 「1日1分読むだけで…」 | 他の本を部分的に読むことで理解が深まるが、まずはこの本で“判断の視座”を養うのが良い |
総括:どれが“最初の一冊”になるか
- 最初の一冊として最も無難なのは、「保険ビジネス 契約者から専門家まで楽しく読める保険の教養」。なぜなら、疑問から始めて構造や制度・未来技術まで幅広く網羅しており、自分が何を深く知りたいかを見定める手がかりになるからです。
- すぐに「何を選べばいいか/コスパの良い保険を見つけたい」という即効性を求めるなら、「NEW よい保険・悪い保険2025年版」が良い。具体的商品比較とランキング形式なので指標が明確。
- 家庭のライフスタイルや家計との調整を重視するなら、「書けばわかる! わが家にピッタリな保険の選び方」が、自分で判断する力を養うのに特に役立ちます。