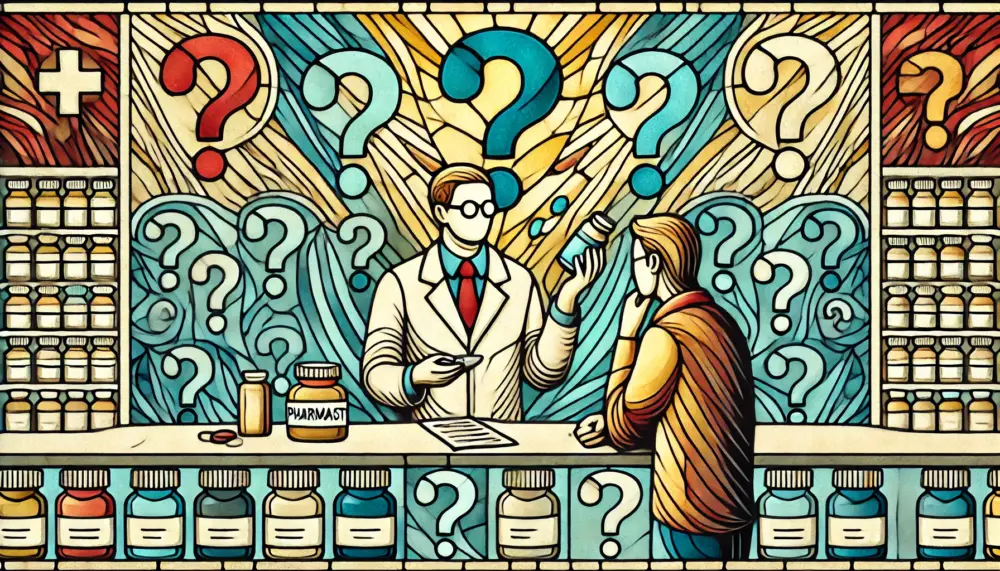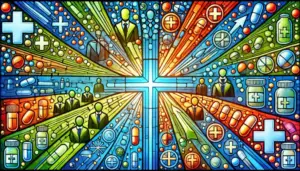薬局での「服薬指導」は、長らく薬剤師の中核業務として位置づけられてきました。
しかし近年、この言葉そのものに違和感を抱く現場の声が増えてきています。
「患者に一方的に話しているだけでは?」
「情報を伝えるだけで“指導”と言っていいのか?」
「AIが説明しても変わらないのでは?」
本記事では、服薬指導の限界と変化を見つめながら、“説明しない”ことがむしろ価値になる時代の薬剤師像を掘り下げます。
✅ 「服薬指導」という言葉が抱える3つの時代遅れポイント
① 「上から目線」のニュアンス
“指導”という言葉にはどうしても**「教える側と教えられる側」という上下関係を感じさせます。
しかし現代の医療では、「患者の主体性」や「共同意思決定(SDM)」**が重視されており、この価値観とズレが生じているのです。
② 情報提供が「目的化」している
- 「この薬は1日3回です」「食後に飲んでください」……
→ それだけで“服薬指導完了”とみなされる空気感があります。
しかし、薬の説明が一方的に終わるだけでは、患者の行動は変わりません。
服薬行動の改善や副作用の予防といった“アウトカム”が伴わない限り、本質的な医療行為とは言えないのです。
③ AIや動画でも“説明”はできてしまう
近年、音声合成による服薬説明やYouTube動画での医薬品ガイドが普及しています。
つまり、「説明するだけ」なら人間でなくても代替可能な時代になっているのです。
📉 一方的な説明では“伝わらない”現実
- 調査によると、服薬指導で聞いた内容を3日以内に忘れる患者は全体の50%以上
- 特に高齢者や初診患者では、「何を説明されたのか分からなかった」と答える人も多数
→ この背景には、一方的な説明・専門用語の多用・確認不足などがあり、
結果として「言ったのに伝わらない」構造が温存されています。
💡 “説明しない”薬剤師とは?その本質は「引き出す力」
ここでいう「説明しない」とは、
「しゃべらない」ことではなく、「一方的に教えるのをやめる」こと。
代わりに重視されるのが、患者の内側から“理解・納得・行動”を引き出す対話型アプローチです。
対話型服薬支援の特徴
| 一方的指導 | 対話型支援 |
|---|---|
| 情報の伝達が目的 | 行動の変化が目的 |
| 質問されなければ終わり | 質問や確認を引き出す |
| 一方向的 | 双方向的・協働的 |
| 知識提供が中心 | 不安・疑問・価値観への対応 |
🛠 “説明しない”薬剤師に必要な5つのスキル
① オープンクエスチョン力
- 「どうしてこの薬を飲むと思いますか?」
- 「この薬について気になることはありますか?」
→ 相手に話してもらう設計で、理解度や不安を可視化できます。
② 傾聴と共感
- 「その気持ち、よくわかります」
- 「副作用が心配になるのは当然ですよね」
→ 安心感を与えることで、“理解しようとする気持ち”が生まれる
③ “情報の切り出し”力
- すべてを一度に伝えるのではなく、患者の関心や状態に応じて必要な情報を優先して伝える
④ “確認質問”の活用
- 「今の説明でご不明な点ありましたか?」ではなく、
→「この薬、何時に飲むことになっていましたか?」と相手に要約させる
⑤ 非言語での伝達力
- アイコンタクト、うなずき、表情、身振り
→ 患者に“安心・信頼”を伝えるのは、言葉以外の要素も大きい
📈 実践による変化:説明しない方が“伝わる”こともある
実際に、対話型の服薬支援を行った薬局では以下のような成果が報告されています。
- 誤薬・重複服薬の発見率が上昇
- 副作用の自己申告が増加(早期対応に繋がる)
- 服薬継続率が上がり、“薬局を信頼する”という回答も増加
つまり、薬剤師が“話す”のではなく“聞く・引き出す”側に回ることで、
患者の行動と結果が大きく変わるのです。
🧭 今後の方向性:「服薬支援士」への進化
「服薬指導」ではなく「服薬支援」。
薬剤師の未来は、“説明者”から“共感型ナビゲーター”へと進化します。
未来の薬剤師像
- 💬 知識で説得するのではなく、感情に寄り添い納得を導く
- 🔍 表面的な症状だけでなく、背景の生活まで読み取る
- 🤝 一方的な指導でなく、患者と並走するパートナー
こうした存在が、AI時代にも“代替不可能な薬剤師”として評価されていくでしょう。
✅ 結論:「説明する」時代は終わり、「支える」時代へ
薬剤師が“伝える”ことにこだわっている間に、
世の中は“患者自身が選ぶ時代”にシフトしています。
だからこそ、
- 何を話したかではなく、患者が何を感じ、どう動いたかが重要
- 一方的な説明ではなく、対話による納得が本質的な価値
「説明しない薬剤師」とは、黙る人ではなく、“引き出す人”である。
これが、これからの薬剤師に必要な新しい常識です。