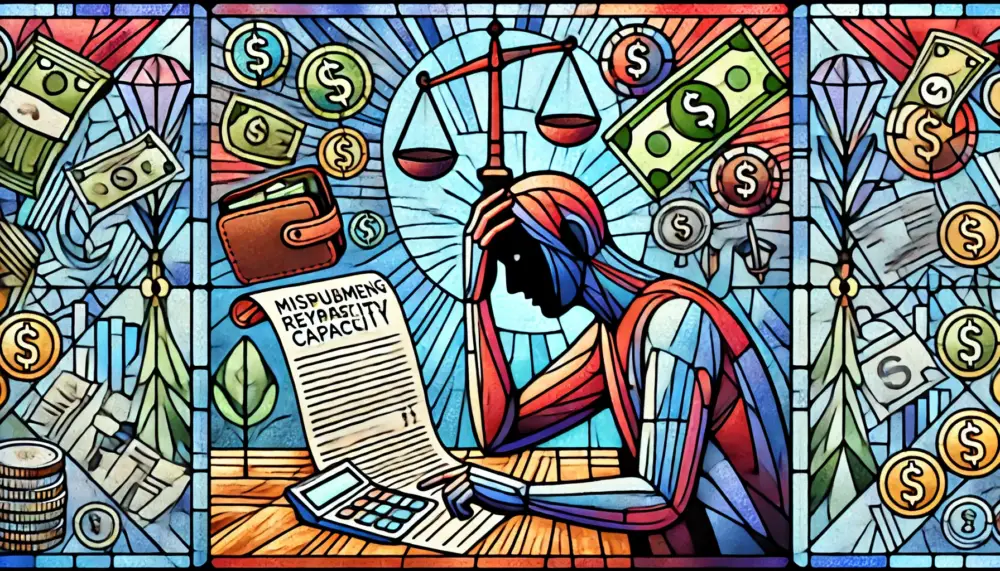はじめに|「審査に通ったから安心」は大間違い
ローン審査に通ったとき、多くの人が「銀行がOK出した=返せる額」と安心してしまいます。
しかし、金融機関が見ているのは**“理論上の返済能力”に過ぎません。
本当の意味で重要なのは、「あなたの生活にとって無理のない返済額」――つまり返済“可能”額**です。
本記事では、ローン返済で苦しむ人たちが陥りがちな思考パターンと、返済可能額を正しく見極める方法について詳しく解説します。
審査基準は「返済できるか」ではなく「貸しても損しないか」
銀行は「この人が返せるか?」ではなく、
「この人に貸しても自社が損をしないか?」という視点で審査します。
審査では以下のような計算が行われています:
- 返済負担率(年収に対する年間返済額の割合)
- 総負債額と他社ローンの有無
- 勤務先・勤続年数・職業安定性
- クレジットヒストリー(信用情報)
つまり、審査に通ったことは「借りる資格」があるだけで、「返済できる保証」ではないのです。
ありがちな“借りすぎ思考”の3つの誤解
❌ 誤解①:「月々の返済額=家賃と同じならOK」
一見もっともらしいこの発想ですが、家賃とローンでは意味合いが全く違います。
- 家賃:修繕費・固定資産税なし、解約も自由
- ローン:維持費・税金が追加発生、返済期間は長期固定
さらに、住宅ローンは35年にわたる超長期契約。
数千円の差が数百万円単位の負担に変わることもあるのです。
❌ 誤解②:「将来の昇給で楽になるはず」
希望的観測で「数年後に年収が上がるから問題ない」と考える人も多いですが、
- 昇給ペースは予測不能
- 転職・病気・育児などで収入が減る可能性もある
- 子どもができると出費が一気に跳ね上がる
“将来の収入”をあてにするのは、家計設計として極めて危険な発想です。
❌ 誤解③:「ボーナス払いで調整できる」
「毎月の返済は抑えて、ボーナス月に多めに払えばいい」と思う人もいますが、
- 景気悪化でボーナスカットされる可能性
- ボーナス支給は保証されていない
- 他の大型支出(旅行、教育、家電など)と重なることも
ボーナスを前提にした返済計画は、家計の爆弾になりがちです。
「返済可能額」を見誤る人の共通点
以下に該当する人は、無理なローン設計になっている可能性が高いです。
| ✅ チェックリスト | 判定 |
|---|---|
| 審査で通った金額をそのまま借りようとしている | YES / NO |
| 将来の支出(教育・介護・転職など)を想定していない | YES / NO |
| ボーナス前提でローンを組んでいる | YES / NO |
| 手元に6ヶ月分以上の生活防衛資金がない | YES / NO |
| 月々の返済額が可処分所得の35%以上になっている | YES / NO |
ひとつでも「YES」がある場合、ローン返済が生活を圧迫するリスクがあります。
正しい「返済可能額」の算出方法
ステップ①:可処分所得を正確に把握する
手取り年収から税金・社会保険・生活固定費を引いた「自由に使える金額」が基準です。
ステップ②:将来の大きな支出を見積もる
教育費、家のメンテナンス費、車買い替え費用など。
最低でも10年間の支出カレンダーを作成するのがおすすめです。
ステップ③:ローン返済は「生活費+予備資金」を確保した上で
余剰資金から捻出できる範囲が本来の返済可能額。
ギリギリの返済計画は“可能”ではなく“綱渡り”です。
具体例:安全な返済設計と無謀な返済設計の差
| 項目 | 安全型 | 無謀型 |
|---|---|---|
| 年収 | 400万円 | 400万円 |
| 可処分所得 | 約300万円 | 約300万円 |
| 年間返済額 | 約72万円(24%) | 約120万円(40%) |
| 生活余裕度 | 高 | 低 |
| リスク耐性 | 高(リストラ・出費に対応可能) | 低(貯金が削られる) |
無理のないローン設計は、「返済しながら生活を楽しめる」バランス感覚が鍵になります。
まとめ|「借りられる額」ではなく「自分が耐えられる額」で判断する
審査に通ったからといって、それが「正解な金額」とは限りません。
銀行はあなたの人生までは見てくれません。
だからこそ、自分自身で「返済可能額」を慎重に見極める必要があります。
- 将来の変化も考慮したライフプラン
- 家計の流動性を守る返済設計
- 精神的・経済的な余裕を残した計画
これらを踏まえた上でローンを組めば、返済は“負担”ではなく“味方”に変わります。