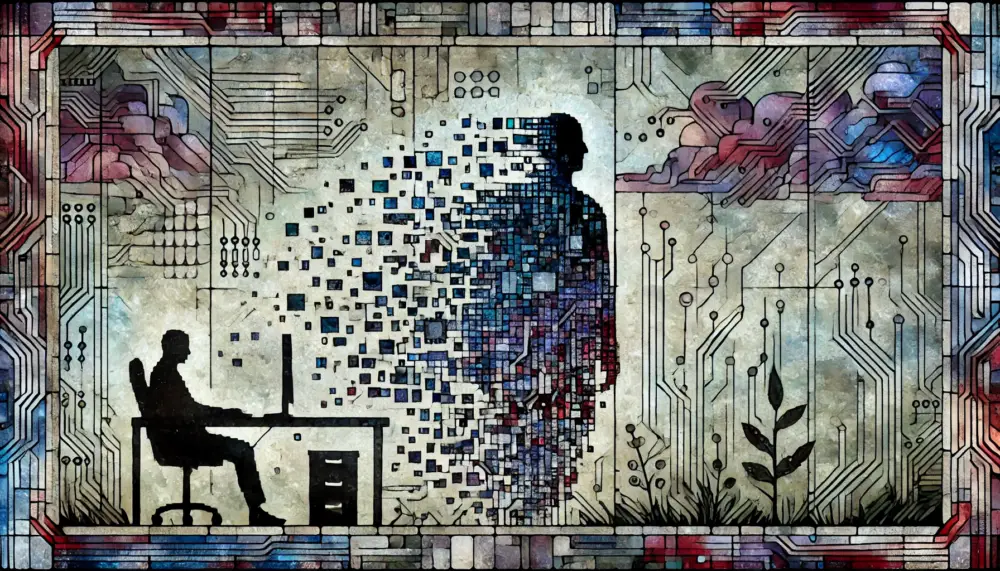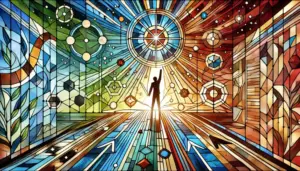はじめに:技術は進化する、でも仕事は残るのか?
「AIに仕事を奪われる」と聞いて久しい今、
ITエンジニアの中にも、「自分の職種は大丈夫なのか?」という不安を抱える人が増えています。
特に生成AIの進化により、
- コードの自動生成
- テストの自動化
- インフラの自動スケーリング
が急速に進むなかで、「3年後に消える職種」「生き残る職種」の境界線はますます不明瞭になっています。
本記事では、“なくなる仕事”と“残る仕事”を分ける基準を明らかにし、エンジニアが今から備えるべき思考法とスキルの方向性を解説します。
1. まず前提:「技術の進化=職種の喪失」は避けられない
✅ 自動化のスピードは“指数関数的”
たとえば、以下のような領域はすでにAI・自動化が浸透しています。
| 領域 | 自動化傾向 |
|---|---|
| フロントエンドUIの生成 | 高(Figma→コード変換等) |
| API連携コードの生成 | 高(ChatGPTで一発生成) |
| 単体テストの自動化 | 中〜高 |
| Webスクレイピング | 高(ノーコード化が進行) |
| インフラ設定 | 中(IaC+自動デプロイ) |
💡 結論:「手を動かすだけの職種」は確実に減る
2. 3年以内に“役割が消える”可能性が高い職種一覧
🔻 消滅・再定義される可能性が高い職種
| 職種 | 理由 |
|---|---|
| マークアップエンジニア | HTML/CSSは自動生成・CMS化で代替可能に |
| 手動テスター | 自動化ツールやユニットテストで対応可能 |
| スクレイピング担当 | GUI型ノーコードツールで代替可 |
| データ取得専門職 | API化・ETL自動化で役割希薄に |
| 一部フロントエンド | LP・フォームなどはテンプレ化が進む |
✅ 傾向:“単一作業系+定型処理+繰り返し業務”は危ない
3. 一方、「残る・伸びる」IT職種とは?
🔺 生き残る/再評価される職種の特徴
| 職種 | 残る理由 |
|---|---|
| テックリード/アーキテクト | 技術の選定・全体設計はAIにできない |
| プロダクトマネージャー | ビジネスと技術の翻訳者として不可欠 |
| セキュリティエンジニア | 状況判断・脅威分析における人間の洞察力 |
| DevOps/SRE | 組織の文脈に応じた運用設計が求められる |
| MLエンジニア | モデル運用・最適化は依然として高度な判断を要する |
💡 ポイント:「文脈」と「判断」を扱う仕事は残る
4. “職種が残るかどうか”を決める5つの思考基準
✅ 境界線は「ツールで代替可能か」ではない
真の境界線は、**“考える力が求められるかどうか”**です。
| 思考基準 | 自問例 |
|---|---|
| 抽象度 | 「自分の仕事は、設計・定義フェーズに関わっているか?」 |
| 文脈依存性 | 「組織や業界に応じて柔軟に対応する余地があるか?」 |
| 判断力の必要性 | 「Yes/Noだけでなく“なぜ”を問う場面が多いか?」 |
| 相互依存性 | 「他職種や部門との連携が前提となっているか?」 |
| 価値創造性 | 「ただこなすのではなく、改善や提案が求められているか?」 |
5. 職種が消えても、“思考スキル”は残る
たとえば、マークアップエンジニアという職種がなくなっても、
- レイアウト設計スキル
- UI/UX思考
- コンポーネントの再利用設計力
などは別職種でも通用するスキルとして転用可能です。
🔧 スキルの“ポータビリティ”を意識せよ
✔ 「職種」に依存するのではなく
✔ 「スキルセット」を汎用化しておく
✔ それが「どの文脈でも戦える力」になる
6. 明日からできるアクションチェックリスト
| 行動 | 目的 |
|---|---|
| 自分の業務を3つのカテゴリに分類:「考える/選ぶ/繰り返す」 | 自動化リスクを可視化する |
| 業務で関わる人の“意図”を意識する | 文脈力と提案力を鍛える |
| 週1回、今の職種がなくなったと仮定して業務を書き出す | スキル転用の視点を養う |
| ChatGPTで自分の作業を再現させてみる | どこまで自動化できるかを把握する |
| 新しい職種に“変換”できるスキルを棚卸しする | キャリア設計の材料を得る |
まとめ:「なくなる職種」ではなく、「通用する能力」を考えよ
生成AI、ノーコード、自動化ツール…。
変化のスピードが加速する今、職種は“名前”で判断しては危険です。
✔ 危ういのは、作業の繰り返しで価値を出している職種
✔ 残るのは、設計・判断・翻訳・交渉・提案といった思考力ベースの職種
✔ 職種が消えても、スキルは“再構築”できる
生き残るのは、仕事に“頭を使っている人”です。