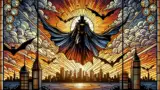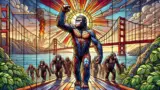普段、ティム・バートンといえば「暗くて不気味」「ゴシック」「闇の美学」が思い浮かぶかもしれません。 しかし、彼の作品には、闇の端でぱっと花開くような「ワクワク感」が確かにあります。 このシリーズでは、そんなバートンの“明るさ”と“冒険心”に焦点を当て、 観る人を驚きと喜びで包む11本の物語を紐解いていきます。
なぜバートンが“闇”だけでなく“ワクワク”を描けるのか? その秘密は、彼の持つ「異形への好奇心」と「想像の拡張力」にあります。 妖しい影の先にある光景、普通の人が踏み込まない場所、 そこにこそ、物語の魔法は宿ります。
— 『ティム・バートン ワクワク編』 編集部
映画一覧(ワクワク編) 🎬











『チャーリーとチョコレート工場』とは? 🍫🎩
『チャーリーとチョコレート工場』は、ティム・バートンが手掛けた夢と皮肉が混じり合うファンタジー映画。 原作はロアルド・ダールの名作児童書で、バートンはそれを大胆に再構築し、「貧しい少年が夢をつかむ物語」をカラフルで奇抜な映像美で表現しました。 登場するチョコレート工場は、まさに“お菓子のテーマパーク”。歯が痛くなるほど甘く、同時にブラックユーモアの効いたバートンらしい世界です。
主人公チャーリーは、家族思いで優しい少年。 ある日、世界中で話題の“金のチケット”を手に入れた彼は、伝説のチョコレート職人ウィリー・ウォンカの秘密の工場に招かれます。 一緒に訪れたのは、世界各国から選ばれた4人の子どもたち。 それぞれが欲・わがまま・過信・無関心を象徴しており、物語はまるで現代社会への風刺劇のようです。
バートンはこの作品で、子ども向けの物語を“視覚のショーケース”に仕上げました。 工場の内部は、チョコの滝、キャンディの木、虹色の草原など、CGとセットを融合させた圧巻のファンタジー空間。 それぞれのエリアが子どもたちの性格を象徴するように作られており、「欲望のテーマパーク」としても機能しています。 光と色のコントラストが強く、まるでお菓子箱を覗いているような感覚です。
ジョニー・デップが演じるウォンカは、奇抜で繊細。 外見はカラフルな衣装にシルクハット、しかし内面は子ども時代の傷を抱えています。 バートンが何度も描いてきた「天才=孤独な存在」の系譜に連なるキャラクターです。 彼の工場は夢の結晶であると同時に、“現実から逃げ込んだ心の避難所”でもあります。
太りすぎの少年、わがままな少女、ゲーム依存の天才少年…。 彼らが次々と失敗していく様子は、どこか痛快で、同時に考えさせられる。 バートンは、「欲をコントロールできない人間」の姿を童話の形式で描いています。 教訓的でありながら説教臭くなく、観客は笑いながらも「自分はどうだろう?」と振り返ることになるでしょう。
バートン映画の多くに共通するのは、「孤独の中で見つける優しさ」です。 しかしこの作品では、チャーリーの家族が温かな絆の象徴となっています。 貧しくても笑顔を絶やさず、夢を信じ続ける姿は、バートンの“希望の物語”の中核を担っています。 最後まで純粋さを失わないチャーリーは、観る人すべてに「本当に大切なものは何か?」を思い出させてくれます。
- チョコ工場のデザインと色使いに注目(バートン流“お菓子の建築美”)
- ウォンカと父親の関係に込められたバートンの原体験
- 音楽:ダニー・エルフマンによるユーモアとリズム感
- 童話×風刺が好きな人
- カラフルで楽しい映像を楽しみたい人
- ティム・バートン映画の“明るい面”を知りたい人
『チャーリーとチョコレート工場』は、バートンが“闇”を脱ぎ捨てて“光”をまとった作品。 『シザーハンズ』で描いた孤独、『ナイトメアー』で描いた夢、それらを統合して「現実に優しさを取り戻す寓話」に昇華しました。 一見子ども向けですが、大人ほど深く感じるものがあります。 甘くて、苦くて、ちょっと皮肉なこの世界――それが、ティム・バートン流の“幸せ”なのです。
総じて『チャーリーとチョコレート工場』は、ティム・バートンの“ワクワク編”の入口にふさわしい作品。 子どもも大人も、自分の中の「純粋さ」を再発見できる映画です。 次章では、もうひとつの奇妙な世界――『アリス・イン・ワンダーランド』を紹介します。🐇🎠
『アリス・イン・ワンダーランド』とは? 🐇🎠
『アリス・イン・ワンダーランド(2010年)』は、ルイス・キャロルの不思議の国の物語をもとに、成長した少女アリスが再び“ワンダーランド”へ戻る冒険を描いた映画です。 挑戦、変化、運命との対峙――ワクワク編としての色彩が強く、バートンらしい幻想と現実の間を行き来する世界観が魅力です。 本作は、彼女がただの幻想を追うのではなく、自分自身と向き合う旅でもあります。
物語は、幼い頃にワンダーランドで体験した奇妙な世界を覚えていないアリスから始まります。 19歳になった彼女は花嫁になる予定を考えられていますが、自分の人生に疑問を抱き続けていました。 ある日、庭のパーティーで白ウサギを見つけ、追いかけた先で穴に落ち、再び不思議な世界へ。 そこでは“赤の女王”による圧政が続いており、アリスは運命に導かれながら、仲間と力を合わせてその国を救おうとします。
本作の見どころは、幻想空間の息づかい。巨大な植物、反転する地形、時間の歪みなど、空間自体がキャラクターのように動きます。 3D技術を活用し、カメラワークが視点を揺らす演出は、観客を物語の中に引き込みます。 色のコントラストが強く、特に赤(女王側)と銀・青(アリス側)の対比がドラマを語ります。
ジョニー・デップ演じるマッドハッターは、この物語で中心的なキャラクター。 彼の“過去の痛み”と“友情”が交錯する描写は、単なる脇役には収まりません。 表情豊かな仕草、不安定な動き、孤独の影――マッドハッターはアリスの旅を影響し、導く存在にもなっています。
作品は、アリスに“運命を受け入れるか”“自分の意志で変えるか”という葛藤を与えます。 赤の女王の支配に抗うことだけが目的ではなく、アリス自身がどう生きるかを問う物語です。 運命に導かれるヒーローではなく、選択を重ねる少女――それがこの映画の強さです.
アリスは幼い頃の記憶と、現在の自分とのギャップに悩む人物として描かれます。 ワンダーランドはかつての記憶の再現だけでなく、成長したアリスの解釈が刻まれています。 観客は“子ども時代の夢”と“現実”の狭間を揺れながら、彼女の選択を追体験します。
- 入口としての“穴落ちシーン”:視点の転換を味わう
- 時間と歪み表現:空間のズレに目を配ると面白い
- コスチュームと色使い:赤 vs 銀・青の対比が意味を持つ
- 夢・幻想的な世界観が好きな人
- ファンタジー+映像美を楽しみたい人
- 自分の運命を問うストーリーに惹かれる人
『アリス・イン・ワンダーランド』は “ワクワク編”の中盤を彩る中心作。 チャーリーが“甘い夢”を見せたなら、アリスは“幻想を現実と重ねる旅”を見せます。 映像の大きさ、選択の重さ、物語の広がり――これらを通じて、バートンは夢と自由を拡張させます.
総じて、『アリス・イン・ワンダーランド』は“心の迷宮”を駆ける物語。 ワンダーランドの驚きと主人公の決意が重なり合い、観る人を揺さぶります。 次章では、人生を語るもう一つの物語――『ビッグ・フィッシュ』を見ていきましょう。📖✨
『ビッグ・フィッシュ』とは? 🐟✨
『ビッグ・フィッシュ』は、「物語」と「現実」が溶けあう、感動的で幻想に満ちた映画です。 親子、記憶、伝承、誇張――それらを美しく重ねながら、人生の深みを描きます。 本作は、ティム・バートンがファンタジーだけでなく人間の感情にも深く切り込んだ一作と言えるでしょう。
物語の中心にいるのは、語り手である父・**エドワード・ブルーム**。 彼は人生を壮大な“冒険談”として語り続けてきました。 一方、その息子ウィルは、父の語る物語を信じきれず、真実を確かめようとします。 エドワードが病床に伏したとき、ウィルは実際の足跡をたどり、語られた物語の裏側にある真実を探し出そうと決心します。
エドワードは、自分の人生を語る過程で、事実を“少し大きく”語ります。 彼の語る物語には、魔女、巨人、不思議な町、サーカスなどが入り混じり、 それらは比喩にも寓話にも聞こえます。 それでも、物語の核心には“真実の感情”があります――つまり、誇張された冒険の中にも本当の思いが隠れているのです。
映画は、ウィルの視点で進みつつ、父の若き日の回想へとジャンプします。 昔話のような挿話が並び、それぞれがウィルの理解を少しずつ変えていく。 この構成は、たとえば「父の語る世界」と「息子の疑問」が対話するように設計されており、観ていて飽きません。
ウィルは父を「物語を語る男」として見てきましたが、それと同時に“遠い人”としても感じています。 映画のクライマックスでは、語ることと受け取ること、言葉の溝と理解の橋がテーマになります。 バートンは、物語を通じて親子が互いを理解し直す道筋を静かに描いています。
- 予告では見えない“町スペクトル”の風景と意味
- 語りの中の“魔女”“巨人”など寓話的登場人物
- エルフマン音楽:幻想と哀愁をつなぐ旋律
- 物語の「裏側」が気になる人
- 親子・家族の物語に心が揺れる人
- 幻想世界も人の心も両方味わいたい人
『ビッグ・フィッシュ』は、ワクワク編の中でも“深みと余白”を与える中核作品です。 前の2章(チャーリー/アリス)が夢と冒険の華やかさを見せるなら、 この章では“物語”の力を通じて人生の意義を問いかけます。 冒険の華やかさだけでなく、心の重みを感じさせるワクワクをここに。
総じて、『ビッグ・フィッシュ』は“語ることの歓び”と“生を祝う悲しみ”を同時に持つ物語。 その豊かな語り口と映像は、観る者の想像力を刺激します。 次章では、ヒーローとしての闇と光を描く『バットマン(1989年)』に進みましょう。🦇
『バットマン(1989年)』とは? 🦇
ダークファンタジー
ティム・バートンの『バットマン(1989年)』は、スーパーヒーローというジャンルに“暗さ”と“ゴシック美”を持ち込んだ画期的な映画です。 単なるアクション映画ではなく、闇と正義、偶像と裏面を映すドラマとして大きな印象を残しました。 今のヒーロー映画が多くこの作品の影響を受けていると言われるほど、そのスタイルは映画の歴史に刻まれています。
舞台は犯罪がはびこる都市ゴッサム。 有名実業家のブルース・ウェインは、幼い頃に両親を殺された過去を持ちます。 彼はその悲しみを力に変え、夜になると“バットマン”として犯罪と戦います。 ある日、街の裏社会で働く犯罪者ジャック・ネーピア(後にジョーカー)は、化学薬品事故で変貌を遂げ、恐怖と混乱を撒き散らしていきます。 バットマンとジョーカーの対決は、街の運命を揺るがす戦いへと発展します。
この映画で特に印象的なのは、都市ゴッサムの描き方。 ビル群、尖塔、闇の影。建築が叫び、街そのものが呼吸するような表現があります。 空間の圧迫感、夜の闇の深さ、街の闇がキャラクターの一部のように感じられます。 ゴッサムはヒーローと悪役の背景であり、観客もその闇の中を歩くような感覚を得られます。
この作品で描かれるのは、ただの戦いではありません。 バットマンもジョーカーも“異質な者たち”でありながら、選択の違いで分かたれています。 ジョーカーは人間の限界を越え、混沌を選び、バットマンは秩序と正義を追い求める。 それは、光と闇、法と無秩序、自由と責任をめぐる対話です。
バートンは闇を“描かない部分”で見せます。 シルエット、暗部の余白、逆光。これらを使って、観客の想像力を引き出します。 そしてダニー・エルフマンのスコアは、重く、神秘的で、感情を揺さぶります。 音楽と静かな場面が組み合わさることで、白熱する戦いがよりドラマチックに映ります。
- バットマンの**マスクと影**:顔を見せずに表情を語る演出
- ゴッサム市街の**アーキテクチャ**:建物の形に込められた意味
- ジョーカーの変身場面:化学事故と“変化”の象徴性
- ヒーロー映画が苦手でも、暗い雰囲気を楽しみたい人
- 都市・建築デザインに興味がある人
- 善悪・正義を哲学的に描く物語を味わいたい人
ワクワク編の中では、一種“闇の覚醒”を描く章です。 これまでの作品が幻想や夢を描いてきたのに対し、ここでは“英雄が闇を抱えて現実と戦う物語”が加わります。 この章があることで、ワクワク編には“冒険”だけでなく“葛藤”の厚みも生まれます。
総じて、『バットマン(1989年)』はワクワク編に“緊張と重み”を添える作品。 観客を楽しませつつ、問いを残すヒーロー映画の金字塔です。 次章では、その続きである『バットマン リターンズ(1992年)』へと進みます。🦇❄️
『バットマン リターンズ』とは? 🦇❄️
ミシェル・ファイファー ジャンル:スーパーヒーロー
ゴシック・ファンタジー
『バットマン リターンズ』は、バートンが『バットマン(1989年)』の続編として描いたゴシックなヒーロー物語。 スーパーヒーローの枠にとどまらず、3つの視点――正義・復讐・欲望――を交錯させた物語です。 闇と幻想、キャラクターの内面を深める演出が目立ち、“ワクワク編”の中で緊張とカタルシスをもたらす章となります。
今作では、ゴッサムに新たな脅威が迫ります。 オズワルド・コブルポット、通称“ペンギン”が、闇の中から町を掌握しようと暗躍。 さらに、発電王であるマックス・シュレック、そして正体を隠した秘書セリーナ・カイル――彼女はある事件をきっかけにキャットウーマンとして覚醒します。 バットマンは、これら複雑な陰謀に立ち向かいながら、自身の孤独と向き合うことになります。
この作品の見どころは、ヒーロー以外のキャラクターでも「怪物性」が強調されている点。 ペンギンは身体的な異形、キャットウーマンは心理と記憶の化身、シュレックは冷酷な資本主義の象徴。 彼らの“闇と欲望”を通して、バートンは“正しい悪”“悪い正義”という問いを巧みに提示しています.
前作よりさらに濃くなったゴッサムの都市像。鋭い塔、寒気を孕む 雪景、無秩序と秩序の交錯。 垂直に突き出る建物が空を切り裂き、暗部が重なりあう街並みが、登場人物の心理を映します。 街自体が“攻撃的な演出装置”になっているような印象を受ける、強度あるビジュアルです。
セリーナは、ある事件をきっかけに記憶と人格が揺らぎ、キャットウーマンに変身します。 彼女の変化は、被虐性と自立欲求の交錯。 バートンは“変身”を恐怖だけでなく、解放や再生ともして描き、キャラクターに厚みを与えています。
- ペンギンの“浮遊シーン”や“軍勢ペンギン”の演出を目で追う
- セリーナ/キャットウーマンの目線と衣装変化に注目
- 影の使い方:暗部の中で何を見せ、見せないか
- ヒーロー映画よりもキャラクターの心理が好きな人
- ゴシック=重厚な世界を映像で見たい人
- 善悪の揺らぎが物語を面白くすると思う人
この章は、ワクワク編に“闇の厚み”と“葛藤の深み”を与えます。 単なる冒険ではなく、欲望と変身、狂気のささやきも含む“重層的な物語”がここにあります。 以後の明るい物語の陰として、読者に深みを残す章です.
総じて、『バットマン リターンズ』はワクワク編の中でも特異な存在。 甘さだけでなく、刃物のような物語も感じさせるバートンの“闇と希望”の交錯。 次章では、ワクワク編の中でも異色作『ビッグ・アイズ(2014年)』へと進みましょう。 🎨👁️
『ビッグ・アイズ』とは? 🎨👁️
クリストフ・ヴァルツ ジャンル:伝記/ヒューマンドラマ
『ビッグ・アイズ』は、実在した女性画家マーガレット・キーンの人生を描いた映画です。 彼女は「大きな瞳の子どもたち」の絵で知られていますが、その絵が“夫の作品”として世に出ていたという実話をもとにしています。 ティム・バートンはこの作品で、夢や幻想ではなく「現実社会の不条理」を繊細に表現しました。
1950年代末、マーガレットは娘とともに新しい人生を歩もうと画家として活動を始めます。 しかし、出会った男性ウォルター・キーンは、彼女の才能を自分の名義で発表し、成功を収めていきます。 マーガレットは次第に絵を描き続けることの意味と、自分の声を取り戻す闘いに挑んでいきます。
「ビッグ・アイズ(大きな瞳)」は、単なる絵の特徴ではなく、感情の象徴です。 マーガレットの絵に登場する子どもたちは、彼女自身の心の鏡。 孤独・不安・希望――そのすべてが瞳の奥に描かれています。 バートンはこの“目”を通して、見る者に「見られる側の痛み」を感じさせます。
ウォルターは“表舞台で輝く男”を演じながら、他人の才能を利用する典型的な虚像の人物です。 一方マーガレットは、静かに描き続ける中で“自分が消えていく恐怖”を感じています。 彼女の戦いは、絵画の著作権という法的問題だけでなく、「女性の声が奪われる構造」そのものへの抵抗でもあります。
バートンにとってこの作品は異例の“現実路線”。 しかし根底に流れるのは、これまでのファンタジー作品と同じ「孤独な芸術家の闘い」です。 『シザーハンズ』や『エド・ウッド』の系譜にある、理解されない創造者の物語として観ると、一層深みが増します。
- 瞳のサイズと描写の変化:感情の揺れを表す細部
- 法廷シーンの象徴性:真実を“描く”瞬間
- バートン作品では珍しい“リアルな社会描写”
- 芸術や創作に興味がある人
- 女性の生き方や表現に共感する人
- バートンの“現実的な側面”を見たい人
『ビッグ・アイズ』は、ワクワク編の中で“静かな革命”を描く作品。 夢や空想ではなく、「現実の中で自分を取り戻す勇気」という新しい希望を提示しています。 その穏やかな色彩の裏に、ティム・バートンの最も人間的なメッセージが隠れています。
総じて、『ビッグ・アイズ』は派手な映像以上に“心の静けさ”で観る作品。 バートンが現実を見つめながらも、夢を捨てないことの大切さを描いています。 次章では、動物と空をテーマにした『ダンボ(2019年)』に進みましょう。🐘☁️
『ダンボ』とは? 🐘☁️
『ダンボ(2019年)』は、ディズニーの名作アニメをティム・バートンが実写化した作品です。 しかし単なるリメイクではなく、「夢を信じる勇気」と「失われたものの再生」を描く感動作に仕上がっています。 バートン特有の幻想的な映像と、人間ドラマの温かさが見事に融合しています。
舞台は、かつて繁盛したが今は落ちぶれたサーカス団。 主人公ホルト(コリン・ファレル)は戦争から帰還した元曲馬師で、片腕を失った彼はサーカスで再び働くことになります。 そこで出会うのが、大きな耳を持つ赤ちゃんゾウ“ダンボ”。 見た目を理由に笑われる存在ですが、彼には「空を飛ぶ」という不思議な力がありました。 ホルトの子どもたちとダンボは、その才能を信じて支え合いながら、自由と希望を探す旅に出ます。
原作の感動をそのままになぞらえるのではなく、バートンは「飛ぶこと」を象徴的に描きます。 それは、欠点とされる“耳”を翼に変えること――つまり「コンプレックスの力への転化」です。 誰かに笑われる存在が、自分の力で空へ飛び立つ。 このテーマは、バートン作品全体に通じる「異端の祝福」でもあります。
サーカス団は、現代社会の象徴でもあります。 個性、見世物、搾取、そして夢。 バートンはその華やかさの裏にある“悲しみと孤独”を繊細に描き、 ダンボが空を飛ぶ瞬間に観客だけでなく自分自身も解放される感覚を与えます。
ホルトの家族、サーカスの仲間たち、そしてゾウの親子――。 それぞれが「失ったもの」を抱えながらも、共に助け合う姿が心を打ちます。 バートンは、この作品で「血縁よりも共感が家族をつくる」ことを優しく描いています。
- ダンボの目と耳の表情:CGとは思えない感情の豊かさ
- サーカスの色彩表現:淡いピンクと青が“希望と悲しみ”を描く
- 空を飛ぶシーンのカメラワーク:視点が観客の心を高揚させる
- 動物が登場する感動映画が好きな人
- 家族で観られる優しい物語を探している人
- ティム・バートンの“優しい側面”を感じたい人
『ダンボ』は、ワクワク編の中でも“純粋な希望”を描く作品です。 『ビッグ・アイズ』で現実と対峙した後、この作品では再び“夢を見る力”が戻ってきます。 ファンタジーと現実の間を優しくつなぐ、再生の物語です。
総じて、『ダンボ』はティム・バートンが長年描いてきた「異端の肯定」の集大成。 飛ぶことができなかった者が羽ばたくとき、観客もまた心を解き放たれます。 次章では、よりスケールの大きな世界『PLANET OF THE APES/猿の惑星(2001年)』へと進みましょう。🪐🐒
『PLANET OF THE APES/猿の惑星(2001年)』とは? 🪐🐒
『猿の惑星(2001年)』は、SF映画の名作をティム・バートン流に“再想像(リイマジン)”した一本。 物語の骨格は「未知の惑星に降り立った人間が、知性を持つ猿に支配された世界と対峙する」というものです。 バートンはここで、ダークな童話作家という顔を少し横に置き、肌触りの異なる「冒険SF」に挑みました。 彼らしい奇妙さは保ちながらも、スピード感あるアクション、肉体的な迫力、異種族の政治ドラマを前面に押し出しています。
物語は、宇宙を航行する任務中の人類パイロットが謎の現象に巻き込まれ、見知らぬ惑星へ不時着するところから始まります。 森林の奥で彼が見たのは、人間を狩り、支配する猿の社会――その世界では、猿こそが文明の中心で、人間は劣位の存在でした。 主人公は、自由を求める人間たちと連携しつつ、友好的な猿、敵対的な猿、それぞれの思惑が絡む中で、自分の存在と任務の意味を探っていきます。
本作の面白さは、価値観の逆転を体験できること。 人間が“弱者”として描かれ、猿が“文明と秩序”を持つ側に立つため、観客は自然と「人間らしさ」とは何かを考えさせられます。 言葉、倫理、仲間意識、恐れ、偏見――そのすべてが猿の社会にもあり、私たちの世界の鏡として働きます。
2001年当時の強みは、生身の役者+特殊メイクの説得力。 顔の筋肉や目線の動きがしっかり見えるため、猿たちの感情が“生きている”ように伝わります。 戦闘や追跡シーンでは体重移動、手指の動き、呼吸のリズムまで丁寧に作られ、アクションの物理感が際立ちます。 CG全盛の今だからこそ、質感の違いが新鮮に映るはず。
ジャングルや岩場などの自然地形と、猿の居住区(砦・市場・儀礼の場)のデザインが見どころ。 自然の荒々しさに、猿の文化がどのように根づいたのかがセットから“語られて”います。 服飾・武具・装飾の素材感も豊かで、文明の層の厚みを感じられます。
ただの冒険ではなく、「誰が誰を恐れ、なぜ支配が生まれるのか」を考えさせる社会寓話です。 恐怖は制度を強く見せ、偏見は対話を妨げる。 主人公が出会う猿の中には、対立よりも理解を選ぼうとする者もいて、そこに希望の糸が見えます。 バートンは、異世界を使って“私たちの世界の問題”を静かに照らします。
- 猿の歩き方・手の使い方:役者の身体表現に注目
- 街並みや市場のディテール:文化の痕跡が見える
- 人間と猿の“呼吸”の違い:対話シーンの間(ま)
- SFの世界観づくりに興味がある人
- “他者理解”をテーマにした物語が好きな人
- アクションとドラマをバランスよく楽しみたい人
『猿の惑星(2001)』は、ワクワク編の中で“スケールの拡張”を担う章です。 家族や心の物語から一歩広げ、文明と文明のぶつかり合いへ。 それでも核にあるのは、バートンがずっと描いてきた「違いの中で理解を探す姿勢」。 アクションに胸が高鳴り、同時に考えも深まる――そんな二層の楽しさがあります。
総じて本作は、ティム・バートンが“異世界の窓”から社会を覗き込んだ挑戦作。 迫力と思想が共存し、観る人に「自分は何を恐れ、何を信じるのか」という問いをそっと残します。 次章では、バートン流の風刺が炸裂する『マーズ・アタック!(1996年)』へ進みましょう。👽💥
『マーズ・アタック!』とは? 👽💥
『マーズ・アタック!』は、ティム・バートンが手がけた“奇妙で笑える地球侵略映画”です。 シリアスなSFではなく、B級映画のパロディとして作られており、 ブラックユーモアと風刺が全開の一本です。 宇宙人の奇抜なビジュアルと、豪華キャストによる大げさな演技が融合し、 バートンらしい“カオスの祝祭”を楽しめます。
物語は、ある日突如として火星人の大群が地球に現れるところから始まります。 当初は平和的な交流が期待されますが、火星人たちは人類をからかい、破壊し、混乱に陥れていきます。 世界中が大パニックに陥る中、誰もが自分の立場を守ることに必死で、 政治家も科学者も市民も、次第に「人間の滑稽さ」をさらけ出していくのです。
本作の宇宙人は、怖いというよりも滑稽で子どもっぽい存在。 彼らは何の理由もなく人類を攻撃し、破壊行動を楽しむように笑います。 その無邪気な残酷さは、まるで「文明ごっこをする子どもたち」。 バートンは、彼らを通じて“理性を失った人間社会”を皮肉っています。
ジャック・ニコルソン、グレン・クローズ、ナタリー・ポートマンなど、超豪華俳優が総出演。 それぞれが“ギリギリの誇張演技”をしており、真面目な場面ほど笑えるという逆説的構造を作り上げています。 シリアスな政治会議も、破壊されるアメリカン・ドリームも、すべてが“お祭り騒ぎ”。 この過剰さこそが、バートンの遊び心です。
『マーズ・アタック!』の本質は、“笑いながら恐怖を感じる”ことにあります。 それは、戦争・メディア・政治・科学といった現代社会の縮図を、 コメディとして描くことで、観客に「私たちは本当に賢いのか?」と問いかけるからです。 ダンボやチャーリーが希望を描いたのに対し、この作品は「絶望の中の希望」を笑いに変える異色作です。
- 火星人の声「アックアック!」のクセになるリズム
- バートンらしい色彩演出:緑・赤・紫のポップな地獄
- ラストの逆転シーン:風刺とユーモアの融合
- バートンのユーモアを全開で味わいたい人
- 社会風刺×コメディが好きな人
- 昔のB級映画の雰囲気を楽しみたい人
『マーズ・アタック!』は、“ワクワク編”の中でも最もカオスで風刺的な作品。 ファンタジーや感動の合間に、笑いと毒を注ぐスパイスのような存在です。 世界の愚かさを笑い飛ばし、同時にどこかで自分を見つめ直す―― そんな“ブラック・ジョークの宝箱”です。
総じて『マーズ・アタック!』は、ティム・バートンが“笑いで爆破した世界”。 不気味でポップで、少し皮肉――それがこの映画の魅力です。 次章では、実在の映画監督を描いた『エド・ウッド(1994年)』を紹介します。🎥🎩
『エド・ウッド』とは? 🎥🎩
マーティン・ランドー ジャンル:伝記
コメディ・ドラマ(モノクロ)
『エド・ウッド』は、“史上最低の映画監督”と揶揄された実在の映画人エドワード・D・ウッド・Jr.を描く、ティム・バートンの温かなラブレター。 派手なファンタジーではなく、映画づくりという夢の現場をモノクロの美しい映像で追いかけます。 失敗しても前へ進む主人公の突き抜けた明るさは、バートンの“ワクワク編”のど真ん中にある「創作の喜び」を体現しています。
物語は、若きエドが映画監督を志し、撮影資金や出演者集めに奔走するところから始まります。 彼は一発逆転を狙うプロデューサーや、仲間の“素人俳優”たちを巻き込みながら、無謀ともいえるスケジュールで映画を撮り続けます。 そんなエドが出会うのが、ハリウッド黄金期の怪奇スター、ベラ・ルゴシ。 落ちぶれ孤独となった彼との友情は、物語の優しい核心です。 ふたりは、過去の栄光と現在の現実の狭間で、それでもカメラを回す勇気を分かち合っていきます。
本作の面白さは、映画を作る過程そのものがドラマになっている点。 ロケ地のやりくり、段ボールのセット、ツギハギ衣装、ワンテイクの連発―― 職人技とは程遠いのに、現場にあふれる熱量は本物です。 バートンは、荒削りでも“仲間で夢を形にする”行為に最大のリスペクトを捧げます。
ベラ・ルゴシは、かつての名声を失い、薬物依存や孤独に苦しむ老優。 そんな彼に寄り添うエドは、偶像ではなく人間としてのベラを見つめます。 ふたりの間に流れるのは、才能の優劣では測れない“作る喜びの記憶”。 友情はドラマを甘くしてしまいがちですが、ここでは静かな尊厳として機能します。
エドは女性服を好み、時にドレスで現場に立ちます。 その描写は笑いの的ではなく、自己表現の一部として提示されます。 バートンは、奇妙さを“変”として排除せず、個性として祝福する監督。 それは『シザーハンズ』から連なる一貫した姿勢であり、ワクワク編の核心でもあります。
本作はあえてモノクロ。光と影のコントラストは、古典映画への愛と同時に、現実のほろ苦さをやわらげます。 夜の路上、薄暗いスタジオ、雨のアスファルト――粒立つ陰影が、登場人物の不器用な気持ちを包み込みます。 ノスタルジックでありながら、決して過去に逃げない視線が心地よい。
- 撮影現場の即興と勢い:無理やりでも進める推進力
- エドが語る“名監督たち”への敬意:憧れが行動を生む
- ベラの所作・言葉遣い:古いスターの矜持が滲む瞬間
- 映画づくりの舞台裏に興味がある人
- “うまくいかなくても続けたい”夢を持っている人
- 弱さや奇妙さをそのまま肯定してほしい人
『エド・ウッド』は、ワクワク編に“創作の源泉”を供給する物語です。 技術や評価よりもまず、好きだから作るというシンプルな衝動。 それは『チャーリー』の夢、『アリス』の選択、『ビッグ・フィッシュ』の語りと響き合い、 バートン世界の根っこにある“つくる喜び”を私たちに思い出させます。
総じて『エド・ウッド』は、“失敗しても笑って前進する”人たちへの賛歌。 大作のような派手さはなくとも、心を温める火のような熱を持った一作です。 次章では、原点のワクワクを体現する『ピーウィーの大冒険(1985年)』へ。🚲✨
『ピーウィーの大冒険』とは? 🚲🎈
『ピーウィーの大冒険』は、ティム・バートンの記念すべき長編映画デビュー作。 主人公ピーウィー・ハーマンの“愛車の自転車を取り戻すための旅”を描いたロードムービーで、 コメディでありながら、バートンの奇妙で夢のような世界観が詰め込まれています。 本作はのちの『シザーハンズ』や『チャーリーとチョコレート工場』へとつながる、「バートン的想像力の出発点」です。
ある日、ピーウィーの大切な赤い自転車が盗まれてしまいます。 世界で一番好きなその自転車を取り戻すため、彼は街から街へと旅に出ます。 道中では、トラック運転手、カウボーイ、ミュージシャンなど、個性的な人々との出会いが待ち受けており、 ピーウィーは自分の“無邪気なエネルギー”で次々とトラブルを笑いに変えていきます。
本作で初めてタッグを組んだのが、作曲家ダニー・エルフマン。 のちのバートン作品に欠かせない“幻想的でリズミカルな音楽”の原型がここにあります。 コメディのテンポとファンタジーの高揚感を融合させ、観客を“奇妙な楽しさ”の渦へと引き込みます。
ピーウィーは大人の外見をしていながら、心はまるで子どものよう。 彼は自分の夢や遊びを誰にも譲らず、笑われても気にしません。 バートンは、この“子どもの純粋さを持った大人”を通じて、自由と想像の価値を語ります。 それは『チャーリー』や『アリス』へ続く“ワクワクの根”でもあります。
道中のエピソードは、まるで夢の断片のよう。 巨大恐竜の看板、幽霊トラック運転手、突然のダンスシーン――すべてが予測不能。 現実の論理よりも“楽しい想像”が優先される世界で、観客は笑いながら自由を体感します。
- ピーウィーの独特なファッションと表情
- セットや背景の細部:おもちゃ箱のような色彩感覚
- 音楽のタイミングとコミカルな編集リズム
- バートン作品の原点を知りたい人
- 笑って前向きになれる映画が好きな人
- 大人でも“子どもの心”を取り戻したい人
『ピーウィーの大冒険』は、ワクワク編の始まりの物語。 後の作品たちが“孤独の中の優しさ”を描くのに対し、ここでは“世界は楽しい場所”だと信じる純粋さが描かれます。 すべてのティム・バートン作品の原点は、この“想像する勇気”にあるのです。
総じて『ピーウィーの大冒険』は、バートン映画の“はじまりの鐘”。 笑いと夢が共存するこの物語は、監督の世界観を最もシンプルに表現しています。 ワクワク編のラストにふさわしい、明るく希望に満ちた作品です。🌟🎬