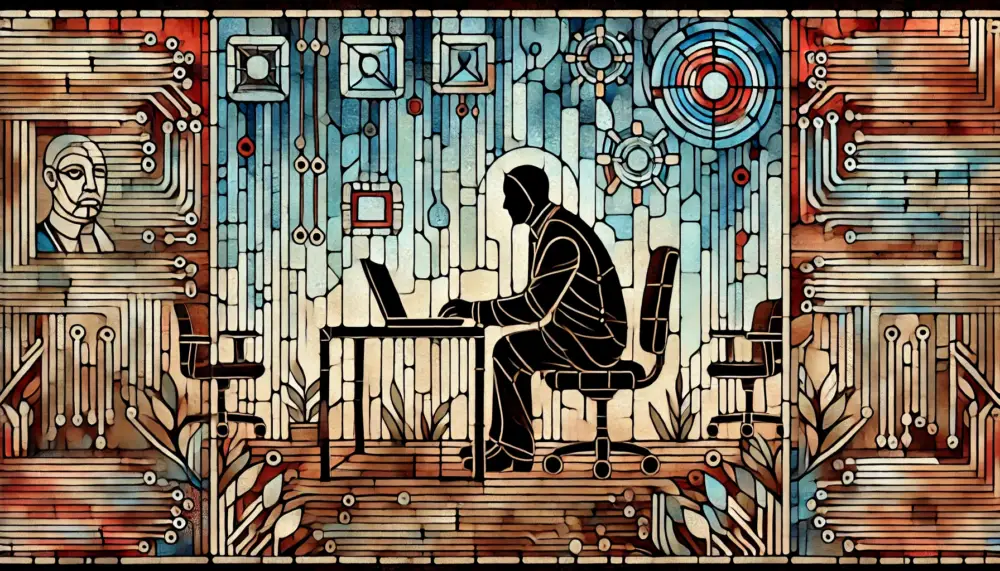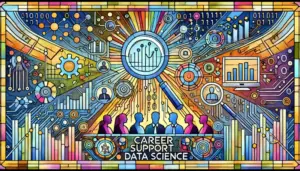はじめに:DXとは、「効率化」の美名のもとに始まる“構造変化”
「うちはDXに取り組んでいます」
「RPAやAIで業務を自動化しました」
「紙文化をやめてクラウド導入へ」
──そんな言葉が並ぶ企業のニュースリリースや社内掲示。
しかし、その裏でひっそりと役割を失い、存在が薄れる職種があるのも事実。
DX(デジタルトランスフォーメーション)は、「選ばれる職種」と「不要になる職種」を静かに分け始めるプロセスでもあるのです。
今回は、なぜエンジニアでも“消える”人が出るのか?
そしてどうすれば「残る人材」「変われる人材」になれるのか?
データと構造をもとに明確に整理していきます。
1. DXによって「消える職種」3パターン
① 「繰り返し作業」に依存する業務
例:
- 定型帳票出力・集計・転記
- 月次ルーチン業務のバッチ実行
- 決まったマクロやスクリプトの実行だけ
📉 → RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)で代替可能
「やるべきことはわかっている。だから自動化できる」という領域。
②「社内専用システムしか知らない」内向きエンジニア
例:
- 独自仕様の古い業務アプリだけを保守
- 外部APIやSaaSと接点がない
- ドキュメントが存在しないローカルルールに精通しているだけ
📉 → クラウド・SaaS導入で一掃されやすい
「この人しかできない」を理由に残っていた業務が、DXで標準化・移行され消える。
③ 技術的には強いが「ビジネス視点」がゼロの人
例:
- 要件を聞かずに技術だけで突っ走る
- 保守性・運用負荷を無視した技術選定
- ビジネス側から「話が通じない」と言われる
📉 → “技術のための技術”は、DXの本質とズレる
DXとは「顧客への提供価値を最大化すること」。
純粋な技術力だけでは価値にならない時代に。
2. 一方で「残る職種」3タイプ
① 自動化の仕組みを“設計”できる人
例:
- どこを自動化すべきか、ROIを見極めて提案できる
- ノーコード・RPA・API連携の仕組みを構築できる
- 現場のヒアリングからプロトタイピングができる
✅ → 「自動化される人」ではなく「自動化を起こす人」になる
② クラウド時代の「システム統合屋」
例:
- SaaS間のデータ同期や連携(例:Salesforce × Slack)
- 業務フロー全体を見たうえでの技術的な接続設計
- セキュリティ・権限管理をふまえたインフラ連携
✅ → “導入すれば終わり”ではない。つなぐ力こそ価値になる。
③ ビジネスの言葉で話せるエンジニア
例:
- KPI、業務指標、顧客体験を踏まえた技術提案
- 現場の非エンジニアと議論ができるコミュニケーション能力
- 「なぜそれをやるのか?」を自分で言語化できる
✅ → 技術は“手段”。価値を届けるための思考力が残る
3. なぜ“変われるエンジニア”と“消えるエンジニア”が分かれるのか?
🔄 DXの本質は「業務の変革」=役割も変わる
技術進化が目的ではない。
組織・業務・サービスのあり方を**再構築するための“手段”**である。
→ 変化に「合わせる」のではなく、「変化に関与する」人だけが残る
📊 評価軸が「稼働量」から「影響力」へ
- 昔:とにかく大量にコードを書ける人
- 今:何をどう改善すれば、どれだけ価値が上がるかを設計できる人
→ 「技術者」ではなく「変革者」になれるかどうかが境界線
🧠 求められるのは“学習力”ではなく“適応力”
- 新技術を次々と覚えることはAIにもできる
- 「どの技術を使うべきか」「どう価値に変えるか」を考えるのは人間にしかできない
→ だからこそ、「考える力×柔軟性」が生き残りのカギに
4. 明日からできる「変われるエンジニア」への3ステップ
✅ Step1:業務フローに目を向ける
- 自分が関わっているシステムは、どの業務のどこを支えているのか?
- どこに無駄や重複があるのか?
📌 → 「この工程は自動化できる」と気づけるだけで、存在価値が変わる
✅ Step2:非エンジニアと話す時間を増やす
- 現場ユーザーの本音、業務のつまずき、欲しい改善は技術書には載っていない
- コミュニケーションの質が、設計力を決める
📌 → 技術“だけ”に閉じこもらないことが武器になる
✅ Step3:DX文脈で自分の技術の“意味”を再定義する
- Pythonのスクリプト → 業務時間を毎日3時間削減する自動処理
- API連携 → 社内部門のサイロを崩す価値提供
📌 → 「何ができるか」ではなく「何を変えたか」で自己紹介を作る
まとめ:「生き残る」のではなく「変わる」ことが戦略になる
✔ DXは、誰かの仕事を奪うのではなく、“役割”を変える
✔ 「技術者」ではなく「変革者」になる人が残る
✔ コードだけでなく“会話”と“設計”に強い人が重宝される
✔ 今こそ、“エンジニア思考”を外に拡張するとき
エンジニアという肩書きが、自動化で薄れていくのでは?
──そんな不安を持っている人こそ、今がチャンスです。
技術だけを使うのではなく、「変化をつくる力」に変えていくこと。
それが“DX時代を生き抜くエンジニア”の条件です。